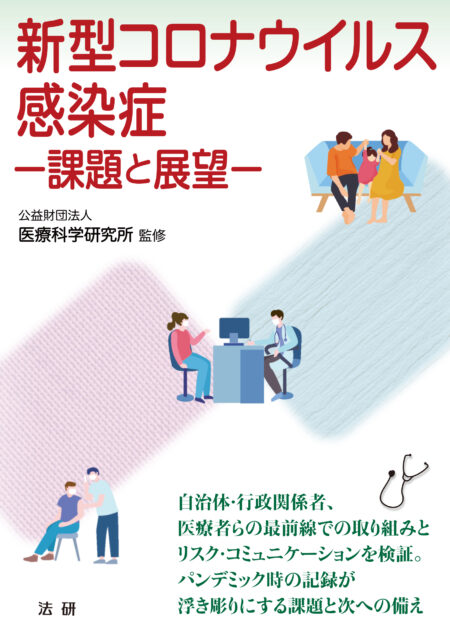-
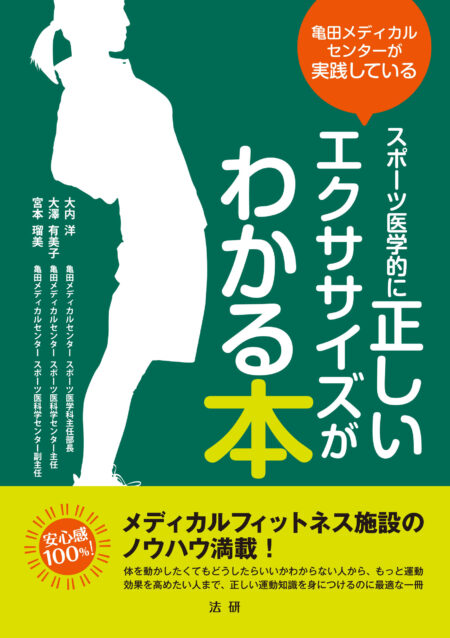
亀田メディカルセンターが実践している
スポーツ医学的に正しいエクササイズがわかる本
¥2,200■メディカルフィットネス施設が推奨し、実践している安全で効果的なエクササイズ!
適切な運動を行うために必要な知識が満載!スポーツ医学的に正しいエクササイズがわかる!
健康づくりのために運動に取り組むのは素晴らしいことです。しかし、そのとき大切なのは、正しい知識に基づいて行うこと。闇雲に行うと、体を痛めたり、ケガをしたり、思わぬ結果を招くこともあります。
あらゆる情報が溢れている今の時代、エクササイズに関する情報もたくさんあります。それらを参考に取り組むのもひとつの方法ですが、中には、スポーツ医学的に効果が期待できないエクササイズが紹介されていることや、もっとひどい場合には健康を害する可能性すらある誤ったエクササイズが紹介されていることもあります。
そこで、そうした情報に惑わされることなく、効果的なエクササイズに安全に取り組むことができるように、医療法42条に定められた「メディカルフィットネス施設」である亀田メディカルセンターが推奨し、実践している「スポーツ医学的に正しいエクササイズ」の知識を1冊の本にまとめました。
エクササイズを行う目的やその人の身体のレベルによって、取り組むべき内容も異なります。メディカルフィットネス施設として、日頃からひとりひとりの状態に合わせて、きめ細かな運動指導を行っている亀田メディカルセンターのノウハウの一端を、本書では図や写真をまじえながら詳しく解説しています。
必要な知識をきちんと身につけて運動をすることは、効果を最大限に引き出し、ケガから体を守ることにもつながります。本書を手に、ぜひ安心・安全なエクササイズに取り組んでください。
-
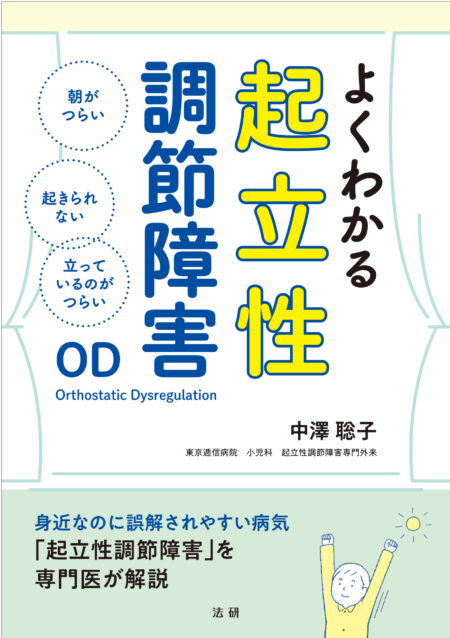
よくわかる起立性調節障害
¥1,870朝は起きられず活力がないのに、午後になると元気が出てきて夜更かしをする…これって病気?不安と疑問にこたえる—■朝がつらい、起きられない、立っているのがつらいのに、理解されにくい。身近なのに誤解されやすい病気「起立性調節障害」を専門医が解説
自律神経の働きや、環境、生活習慣、体質、からだの成長などがかかわり、朝起きて活動したり、立った状態で長くいることがつらい、できないという悩みを持っている人が多くいます。起立性調節障害(OD)の人は昔からいたのですが、理解されないことも多く、誤解されがちでした。
症状が朝に強くなることが多く、午後や夕方以降は元気になって遊んだり、ふつうに生活できることから「さぼっているのでは」「なまけているのでは?」と思われてしまいがちです。通学に耐えられず不登校につながることも多いのですが、朝寝坊して、日中はゲームをして過ごしたりしている様子を見ると、「学校でいやなことがあったのでは」「こんなに体力がなくてこの先大丈夫なのか」と保護者は心配になってしまいます。起立性調節障害の症状は多様です。そして個人差もあります。
症状に思い当たる場合は受診も検討するとよいでしょう。生活の工夫や、周囲のサポートでつらさが軽減することも多いです。 読みやすい本文に加えて、イラストや図解を多用しています。
患者さんが思春期であることも多いので、成長に合わせたかかわり方やコミュニケーションの考え方についても書かれているので、治療の際の参考になります。起立性調節障害は遅刻、不登校などにもかかわりの深い病気です。
症状は多様なので、ケーススタディを多く紹介しています。発症の時期は、学業の進め方、進路選択なども気になる年頃です。本人や家族は、治療をして一刻もはやく元気に毎日学校に通えるようにと思いますが、すぐに回復する例ばかりではありません。病気の治療をしたり、病気・症状を理解して受け入れ、うまくつきあっていく方法を模索したりすると同時に、進路についてもお子さんごとにそれぞれの道を見出して力強く進んでいく様子が伝わってきます。 -
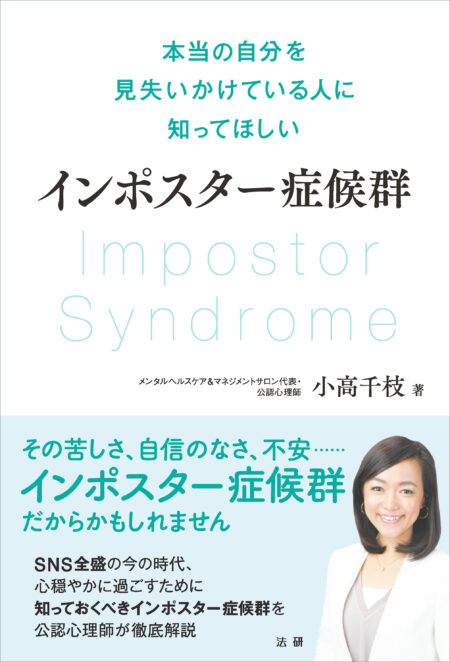
インポスター症候群
本当の自分を見失いかけている人に知ってほしい
¥1,870自分を見失ってしまうことが簡単に起こりがちな今の時代に知っておきたい「インポスター症候群」を人気の公認心理師が徹底解説■70%の人が1度は経験するという報告もあるインポスター症候群を徹底解説。偽りの自分を演じることで感じる息苦しさを楽にするヒントが満載!
「自分に自信が持てない……」
「周りから期待されることが息苦しい……」
「本当はたいした人間でないと、いつ悟られるか不安……」こうした悩みを抱えている人はたくさんいると思います。
そんな方にぜひ知っていただきたいのが「インポスター症候群」です。インポスターには「詐欺師」や「偽物」といった意味がありますが、インポスター症候群(impostor syndrome)とは、自分を肯定することができないため、周りから称賛されても、それを受け入れることができず、詐欺師のように周りを「騙している」という感覚に陥ってしまう心理傾向のことです。
日本ではまだあまり知られていませんが、70%の人が人生で1度はインポスター症候群を経験したことがあるという研究報告もあるほど身近なもので、海外ではインポスター症候群に苦しんだことがあると表明している著名人がたくさんいます。・実績や仕事ぶりを認められても「自分の実力ではない」「周りのおかげ」「運が良かっただけ」「次回もうまくいくとは限らない」などと捉えてしまう人
・昇進を打診されても「自分は適していない」と思って固辞してしまう人こうした人はインポスター症候群に陥っている可能性がありますが、謙遜を美徳と捉えがちな日本人はインポスター症候群に陥りやすい面があり、広く知られてほしい概念です。
特にSNSがこれだけ普及した社会を生きていくうえで、インポスター症候群について知っておくことは、とても大切なことです。なぜなら、SNSを駆使することで、以前よりも簡単に注目を集めやすい時代になりましたが、何の前触れもなく急激に注目を集めると、環境の激しい変化に気持ちが追いつかないことが珍しくありません。自分が望んだことにもかかわらず、いざ叶うと自分を見失ってしまい、「こんなの本当の自分ではない……」と苦しんでしまうことがよく起こります。
また、インポスター症候群は男性よりも女性の方が陥りやすい傾向があります。聡明で有能な女性、高いキャリアを築いている女性や専門職の女性に多く見られる傾向があることから、女性活躍推進の一環で女性管理職の比率向上が求められている中、インポスター症候群について知っておくことは、企業の人事労務の観点からも重要になってきています。
(自分が自分じゃないみたい……)
こうした悩みを抱えながら過ごすことは、苦しいものです。しかし、その原因がわかれば、対処法が見えてきます。その息苦しさを、きっと楽にすることができるでしょう。
本書は、公認心理師であり、早い時期からインポスター症候群に注目してきた著者が、インポスター症候群の基本的な知識から克服に繋がるヒントまでを、余すことなく書き切ったものです。カウンセラーとしての豊富な経験をもとに、セミナーや講演などで語られてきた内容が、ぎっしり詰め込まれています。本当の自分を見失いかけているすべての人に届けたい充実の1冊です。
-
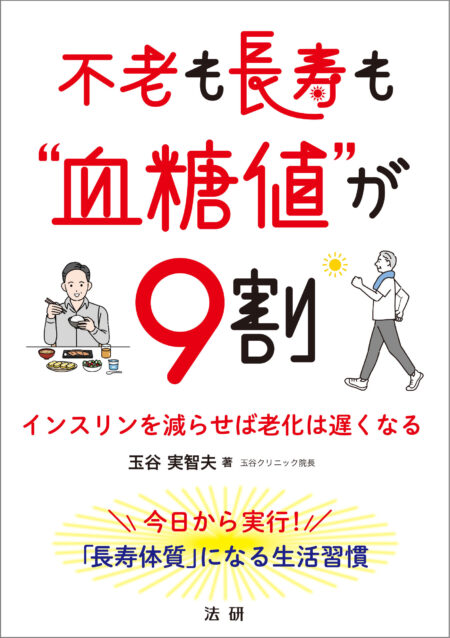
不老も長寿も“血糖値”が9割
¥1,760~インスリンを減らせば老化は遅くなる~不老長寿達成のための生活習慣 新バイブル老化を遅らせ、健やかに寿命を伸ばすための座右の書
「老けない」「長寿」をキーワードにした本が売れています。特に本書はこれまでにない「血糖値と老化」に新しい切り口を提示します。「血糖を体内に取り込むインスリンそのものが、実は老化の大きな原因である」。近年証明されたこのエビデンスと「長寿ホルモン」アディポネクチンの知見を踏まえ、“老化をとめる方法”をわかりやすく解説し、食生活・運動習慣の両面から実践できます。
著者は米国で老化のメカニズムを研究した後、日本で糖尿病・生活習慣病の治療に当たっている医学博士で、理論と実践の両面から解説します。
■本書の特長
・血糖値とインスリンとの関係から老化を抑えるしくみを解説
・糖尿病予備軍の方の症状を進ませないヒントを紹介
・不老長寿になるための「長寿的生活習慣」(食生活編、運動習慣編)を解説 -
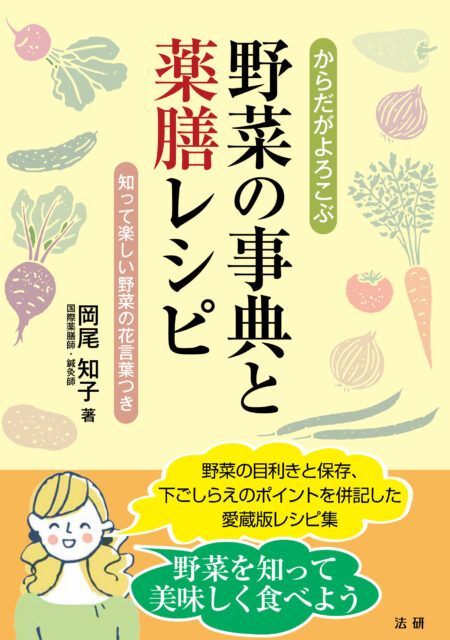
からだがよろこぶ野菜の事典と薬膳レシピ
¥1,760~知って楽しい野菜の花言葉つき~美味しい野菜のカラー愛蔵版■野菜の花言葉が添えられた愛蔵版レシピ集
野菜にも花言葉があるということは、意外と知られていませんが、「私に触らないで」(ゴボウ)「恋の病」(オクラ)などユニークな花言葉がつけられています。また、美しい花を咲かせる野菜もたくさんあります。野菜の花の可憐さや、花言葉を知ることをきっかけに、それぞれの野菜の由来や栄養、日々の健康に役立つ薬膳のレシピまで紹介し、読み物兼レシピ集として手元に置いて楽しんでいただけます。
■本書の特長
●野菜の花のカラー写真と解説に、野菜の花言葉を添えた楽しめる読みもの&レシピ集
●身近に手に入る野菜ばかり。自分の体質・体調、季節に合わせた美味しいメニューを紹介
●それぞれの野菜の旬と目利き、保存方法、下ごしらえのコツを併記した実用使い版
●基本は漢方の教えにもとづく野菜の薬膳レシピ集。体の不調を積極的に改善できる -
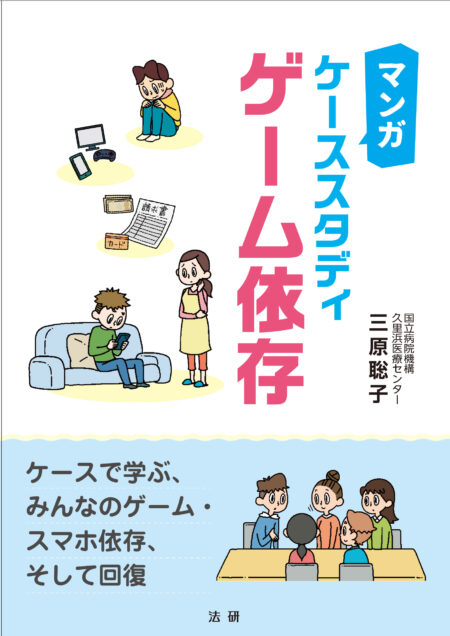
マンガ ケーススタディ ゲーム依存
¥1,870
―ケースで学ぶ、みんなのゲーム・スマホ依存、そして回復多年に渡り専門外来でゲーム依存患者・家族への相談・支援にあたってきた著者による、ゲーム依存への働きかけ、その後をマンガで紹介●ゲーム依存への働きかけ、かかわり方のヒントに
インターネットゲーム障害(ゲーム依存)が世界保健機関によって精神疾患として位置づけられるなか、スマホやネット環境はさらに普及し、必須の存在となっています。誰もが使っているインターネット技術ですが、多くの人が便利に活用する一方で、のめり込んでバランスを失い、リアルの生活が破綻するほど没頭してしまう人がいます。
ゲーム依存に陥ってしまう事情や環境は人それぞれです。本書は、依存症治療専門の医療機関である久里浜医療センターで長年患者・保護者のカウンセリング、支援にあたってきた著者が、その経験から、多くのケーススタディをマンガで紹介し、ポイントを解説することで、さまざまな家族模様から見えてくる悪循環からの脱却のヒントを探ります。
■ゲーム依存の特徴
●ゲーム使用をコントロールできない。
●生活のなかのなによりもゲームを優先。
●問題が起きていてももっとゲームをしたいと思う。 -
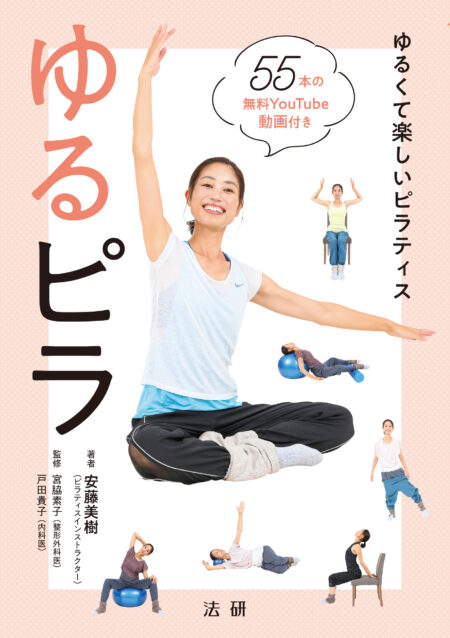
-
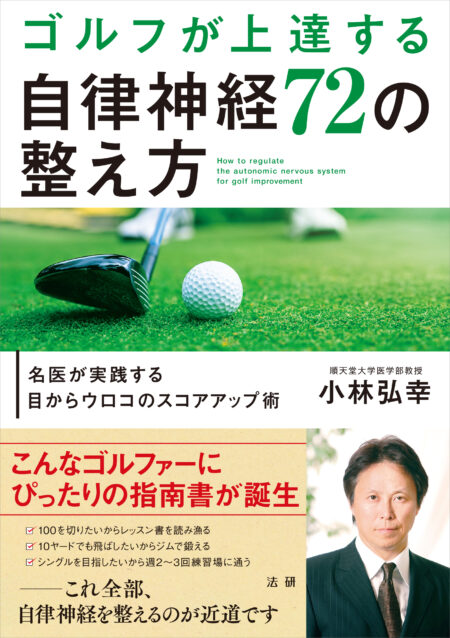
ゴルフが上達する自律神経72の整え方
¥1,650自律神経の安定があなたのゴルフを変える!名医が実践する目からウロコのスコアアップ術
ゴルフのスコアをアップする一番のカギは自律神経のバランスを崩さずにラウンドすること。自律神経研究の第一人者にその秘訣を学ぶ!
■自律神経の安定があなたのゴルフを変える!
「100を切りたい!」「10ヤードでも飛ばしたい!」「シングルを目指したい!」――そんなゴルファーの望みを叶える目からウロコのスコアアップ術。それは自律神経を整えることです。
運動不足、ストレス、生活リズムの変化などにより自律神経が乱れると、健康に悪影響を及ぼすことが知られていますが、自律神経はスポーツのパフォーマンスにも深い関わりがあります。
特にゴルフでは、自律神経の影響がラウンド中にはっきり表われます。自律神経が整っているときは、迷いも不安もなく、いい流れでプレーできますが、自律神経のバランスが崩れると流れが変わり、スイング、スコア、プレー内容が噛み合わなくなることが少なくありません。
自律神経のバランスは、ほんの些細なきっかけで崩れることも珍しくなく、雨、風、寒さ、暑さといった「気象条件」、前夜の過ごし方、車の運転、食事のとり方といった「ゴルフ以外の生活や事前の準備」など自分では気がつきにくいこともたくさんありますが、ラウンド中に自律神経が乱れる理由は、そのほとんどが「プレーに余裕がない」「判断に迷いがある」「欲をかいた」「人前で見栄を張る」「ボールの状況が悪い」のどれかです。
そうして自律神経が乱れたままプレーをすると、ミスにつながります。ミスをするのは、スイングが悪いわけでも、技術不足でもありません。ほとんどのミスは打つ前に理由があるのです。逆に考えれば、ラウンド中、自律神経が安定しており、もし自律神経が乱れても立て直すことができれば、ショットもパットも落ち着き、確実に今よりスコアをアップすることができるのです。
本書は自律神経研究の第一人者で、大のゴルフ愛好家でもある順天堂大学医学部の小林弘幸教授が、これまで重ねてきた研究と自身のゴルフで取り組んできたことを踏まえて、ゴルフのスコアアップにつながる自律神経の整え方を72のポイントにまとめました。
一度悪い流れになると引きずってしまう……
練習ではうまくできるのに、本番では失敗してしまう……
いくらスイング改造に取り組んでも、力を発揮できない……
そんな方は、ぜひ本書をお読みいただき、自律神経をコントロールする方法を身につけてみてください。高度な技術を身につけようとするよりずっとシンプルに、早く、ゴルフのパフォーマンスがアップするでしょう。 -
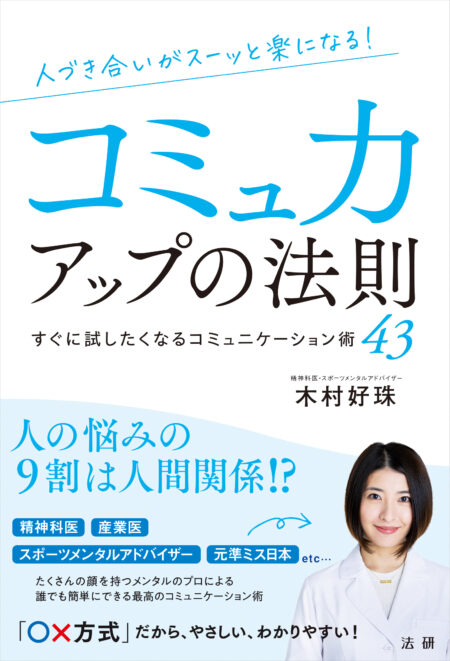
人づき合いがスーッと楽になる コミュ力アップの法則
¥1,650元準ミス日本の精神科医に コミュニケーションを学ぶ!すぐに試したくなるコミュニケーション術43“心のプロ”である精神科医が実践している説得力抜群のコミュニケーション術を大公開
ストレスの原因として真っ先にあがるものといえば人間関係。学校でも、仕事でも、プライベートでも、多くの人が人間関係に悩みを抱えます。しかし、そんな人間関係もコミュニケーションがうまくいけば楽になり、ストレスを軽減することができます。本書はそうした対人関係を楽にするためのコミュニケーション術を、メンタルのプロフェッショナルである精神科医が余すことなく書きあげた一冊です。【本書のポイント1】
メンタルのプロフェッショナルである精神科医が実践しているコミュニケーション術が学べる精神科医の診察室における最初の仕事について、著者は「患者さんに“この人なら話しても良いな”と思わせる場を作ること。でも、話すことに抵抗がある患者さんにとって、それはとても難しいこと」と言います。
患者さんに“話しやすい”“話してみよう”と思ってもらうことは治療の第一歩。そのために著者は診察時に積極的に雑談を取り入れるなど、周りから時に精神科医らしくないと言われながらも、一人ひとりの患者さんと良好な関係を築くために努力を重ね、コミュニケーション力を磨いてきました。【本書のポイント2】
多種多様な人のメンタルを適切にサポートしてきた経験と実績に基づいた抜群のコミュニケーション術著者はかつて準ミス日本に輝き、医大生アイドルとして芸能活動も経験してきました。現在は「みんなが心地良く、笑顔でいる時間を作りたい」をテーマに、日々メンタルクリニックで患者さんと向き合いながら、いくつもの企業で産業医を務めつつ、数々のスポーツチームやアスリート個人のメンタルサポートも行うなど、スポーツメンタルの分野でも大活躍しています。
このようにいろいろな顔を持ち、多方面に活躍の場を広げている著者ですが、その原動力となっているのが、高いコミュニケーション力です。患者さんやオフィスワーカー、トップアスリートやジュニアアスリートといった多種多様なたくさんの人たちと、何年にも渡って毎日触れ合う中で培われたコミュニケーション力は本物です。精神科医として、産業医として、スポーツメンタルアドバイザーとして、どんなタイプの人のメンタルも、上手にサポートしてくることができたのは、そのベースに抜群のコミュニケーションスキルがあったからに他なりません。
本書は、そんな著者ならではの実践的なコミュニケーション術がギュッと詰まっています。【本書のポイント3】
対話で大切な「伝える力」と「聞く力」を伸ばす43の実践的なスキルを紹介本書を読むと、「伝え方」や「聞き方」、「考え方」や「受け止め方」を少し変えるだけで、コミュニケーションにおいて改善できることがたくさんあることがわかります。それも決して難しいことではありません。「言われてみれば納得」「これなら簡単にできそう」「早速やってみよう」――そんなふうに思えることばかりです。
精神医学の専門家として、時に心理学の知識などを交えながらも、語り掛けるようにやさしく、○×方式でわかりやすく、誰でも簡単に取り組めることを伝えてくれます。コミュニケーションが苦手な方から、より良い人間関係を築きたい方まで、人づき合いを楽にするヒントを、きっとこの本の中に見つけることができるでしょう。 -
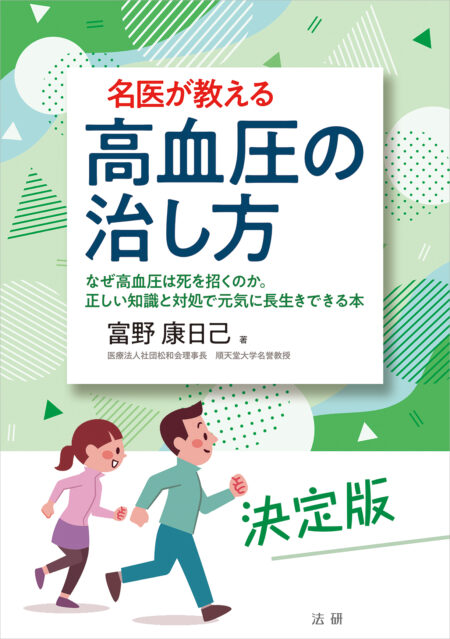
名医が教える 高血圧の治し方
¥1,650健康長寿を助ける決定版なぜ高血圧は死を招くのか。正しい知識と対処で元気に長生きできる本●放っておくと心筋梗塞や脳卒中など、重大な事態を引き起こす高血圧と動脈硬化。自覚症状なく進んでしまう油断のならないサイレントキラーです。
●ウイルス等に感染することで、重篤化させる基礎疾患の一つとしても見逃せません。
●わが国では推定4300万人もの高血圧患者さんがいるといわれており、高血圧が原因となって死亡する人の数は、年間10万人は下らないと見積られています。その多くは自覚症状がないことから取り返しのつかない事態に陥っているのです。
●しかし、高血圧は決して治せない病気ではありません。対処が早いほど改善のきく症状なので、高血圧について正しく知っていただくことが何よりも大切です。 -

大切な人を亡くした人の気持ちがわかる本
¥1,980喪失を体験した人への理解と支援グリーフケア 理解と接し方グリーフケアが注目されている
がん診療の現場などを中心にグリーフケアの大切さが徐々に知られるようになってきました。病気による死別以外に、自殺や災害、事故による死別も注目されてきています。
第三者は死者に注意が行きがちですが、現実には残された遺族へのケアが切迫しています。遺族の精神疾患や自殺率の高さは統計にも表れています。
残された遺族や身近な人たちが「死」とどのように向き合うかは、普遍的な課題であると同時に、感染症の流行、自殺率の増加、超高齢化に伴う死別の増加など、喫緊の課題でもあります。「グリーフケア(悲嘆のケア)」については、今後ますます注目されてくるでしょう。
悲嘆のあと心がたどる道筋を知る
死別の状況、死者との関係性などによって、遺族に起こる心理的な反応は変わってきます。たとえば犯罪・事故被害による死別などは、トラウマ的な影響を残します。また子どもと大人では反応の現れ方も異なります。周囲の「善意の励まし」が遺族を苦しめてしまうことも少なくありません。
本書はグリーフにある人の心理や情動の変遷を理解するとともに、より相手の負担とならない関わり方、コミュニケーションへの考え方を紹介します。死別後、どのような反応が現れるのか、どのように受容していけるのか、道筋を知ることで、グリーフにある人の心の負担を軽くし、適切な接し方が見出せるようになります。