-

最先端治療 子宮がん・卵巣がん
¥2,750国がん中央病院 がん攻略シリーズ第5弾!国がん中央病院 がん攻略シリーズ子宮がん、卵巣がん治療の最前線がわかる1冊
子宮頸がんや子宮体がん、卵巣がんなど女性特有のがんは、ほかの臓器のがんに比べ、やや若い世代で発症することが少なくありません。さらに、これらは生殖にかかわる臓器、女性性を支える臓器であるという特徴があります。子宮や卵巣を取り去ることにより、その機能は少なからず失われる可能性があり、とりわけ妊娠できる力=妊孕(にんよう)性(せい)の問題は、患者さんによっては、治療後の生活にも大きくかかわってきます。
本書では、最先端の研究が進む検査・診断法や治療法の動向、治験・臨床試験による有効な分子標的薬の最新知見を紹介するとともに、がんゲノム研究や遺伝性腫瘍の取り組みについても紹介しています。また、治療後のQOLを高めるための心身の苦痛すべてに対応する緩和ケアの重要性に着目し、さまざまな視点から解説しています。
国がん中央病院における子宮がん、卵巣がんの最先端治療がわかる1冊。安心して治療に臨むためにお役立てください。
●日本のがん治療の最前線・国がん中央病院が実践する最新の子宮がん、卵巣がんの最新治療の情報を紹介
●最先端の研究が進む検査・診断法や治療法の動向、有効な分子標的薬の最新知見を掲載
●がんゲノム研究、遺伝性腫瘍の取り組みも掲載
●生殖機能にかかわる婦人科がんの特性を踏まえ、QOLの重要性にも注目 -
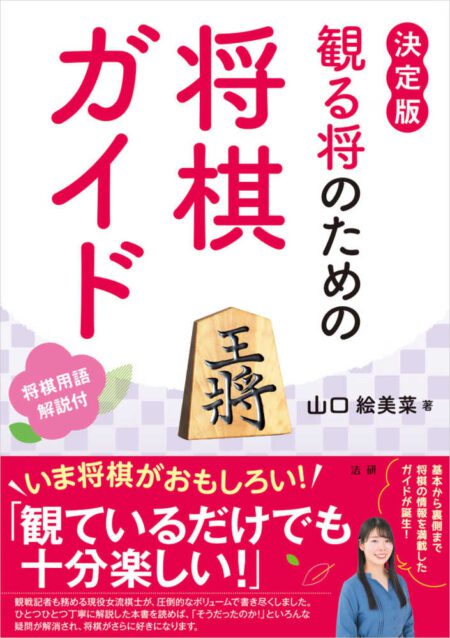
観る将のための将棋ガイド
¥1,760観る将のために作られた将棋ガイドの決定版!今、将棋が面白い!見ているだけでも十分楽しい今、空前のブームを迎えている将棋界。そんな将棋に関する様々な情報を現役女流棋士が書き尽くした「観る将」待望の1冊が誕生!
今、急増している「将棋を観るのが好き」という新しいタイプの将棋ファン「観る将」。そんな観る将を強力にサポートする新発想の将棋ガイドが誕生しました。全9章、400ページを超える圧倒的なボリュームで、多岐にわたる将棋情報をやさしく、わかりやすく、丁寧に解説。毎日新聞の観戦記者でもある現役女流棋士が、出し惜しみすることなく書き尽くしました。基本から裏側まで将棋情報がぎっしり詰まった本書を読めば、将棋への理解が一段と深まり、将棋がもっと楽しく、おもしろくなることは間違いないでしょう。指す、観る、描く、撮る、読む――思い思いの形で将棋を楽しんでいるすべてのファンに届けたい著者渾身の1冊です。682語におよぶ将棋用語解説付。 -
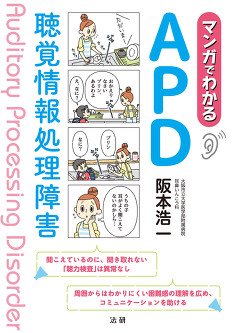
マンガでわかるAPD 聴覚情報処理障害
¥1,760聴覚には異常がないのに、聞き取ることが難しい聴覚情報処理障害(APD)がよくわかる聴覚には異常がないのに、聞き取ることが難しい
音は聞こえているのに、その情報を処理する過程に障害があり、うまく聞き取ることができない聴覚情報処理障害(APD:Auditory Processing Disorder)。最近になって知られるようになりました。聞き取りにくいといっても聴覚には異常がないことも多く、本人も原因がわからず困っています。相手の言うことがわからなかったり、聞き取れなかったりすることでコミュニケーションがうまく取れず、人間関係の悩みを抱えてしまうこともあります。
本書は耳鼻咽喉科での診療を行っている医師によるAPDの基礎知識や現在わかっている対処法について、マンガをまじえながら詳しくわかりやすく解説した一冊です。
◆ 参考文献 ◆
・小渕千絵 著『APD「音は聞こえているのに 聞きとれない」人たち ―聴覚情報処理障害(APD)とうまくつきあう方法』(2020年 さくら舎)
・小渕千絵 著『APD(聴覚情報処理障害)がわかる本 聞きとる力の高め方 (健康ライブラリーイラスト版)』(2020年 講談社)
・加我君孝 監修 小渕千絵ほか編著『聴覚情報処理検査(APT)マニュアル』(2021年 学苑社)
・平野浩二 著『聞こえているのに聞き取れないAPD【聴覚情報処理障害】がラクになる本』(2019年 あさ出版)
・『「よく聞こえない」ときの耳の本 2021年版 (週刊朝日ムック)』(2021年 朝日新聞出版)
・中野泰志監修『新しい 心のバリアフリーずかん』(2018年 ほるぷ出版)
・福西勇夫 福西朱美 著『マンガでわかる発達障害 特性&個性 発見ガイド』(2018年 法研)
・谷原弘之 著『事例でわかる発達障害と職場のトラブルへの対応』(2018年 法研)
・高貝就 著『子どもの発達障害家族応援ブック』(2013年 法研)
◆ 訂正 ◆
本文41ページの「質問票(チェックリスト)による聴覚認知検査」音声聴取の質問項目2~3に誤りがありました。
正誤表は↓こちら↓からダウンロードをお願いします。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけしております。≫ APD正誤表
-
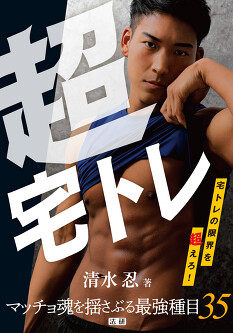
超宅トレ
¥1,650宅トレの限界を超えろ!マッチョ魂を揺さぶる最強種目35「自宅で自重トレーニングをしても、筋肉はデカくならない」。こうした声は、筋トレ経験者からよく聞きます。しかし、本当に器具やマシンがない環境では、筋肥大は起こせないのでしょうか?
プロアスリートなどのパーソナルトレーナーを務める著者によると、答えはNO。どんなに鍛え上げた肉体の持ち主であっても、やり方次第で、宅トレでも十分に追い込み、さらに鍛え上げられるといいます。
本書は、著者が長年の経験で辿り着いた宅トレで筋肥大を起こすための秘訣を、筋トレ中・上級者に向けて徹底解説した本です。特別な器具やマシンは使わずに、筋肉に強い刺激を与えられるハイレベルなエクササイズ=「超宅トレ」を35種目厳選しました。
筋トレ中・上級者なら既に熟知しているだろう一般的な説明は極力省き、筋トレの精度を上げるために必要な「なぜこの動作をするのか」という理論と「動作中にどこに意識を向けるか」のポイントの解説に特化しました。また、35種目全てに著者本人による動画の解説を付け、よりマニアックなレベルで動作の確認ができるようになっています。
コロナ禍でジムから足が遠ざかり、自己流の宅トレに限界を感じている―。そんな葛藤を抱えたマッチョ達を満足させられる、宅トレを超えた宅トレ本になりました。
本書の特徴
・マシンや器具不要! 筋トレ中・上級者も納得のハイレベルな35種目を厳選
・著者本人による動画解説付き。よりマニアックに動作を細かく確認できる
・一般的な説明は極力省き、筋トレの精度を上げるための「理論」と「意識」の解説に特化 -

健康情報は8割疑え!
¥1,540京大医学部のヘルスリテラシー教室自分にとってベストな治療法を、どのような情報をもとにどう決めればいいか「ワクチンは接種しないほうがいい」「この病気にはこの治療法がよい」「これを食べれば病気がよくなる」……あなたはそのような情報を目にしたとき、「根拠」についてどう感じていますか? そしてどう解釈し、どう行動していますか?
テレビで著名な人が発信しているから、専門家の監修がついているからといって、信頼がおける情報とは限りません。また、信頼度が高く効果のある治療法であっても、同じ病気の人すべてに当てはまるかどうかはわかりません。
本書は、医療・健康情報を理解して活用できる力=「ヘルスリテラシー」指導の第一人者である著者が、初めて一般の人向けにヘルスリテラシーを語った本です。新型コロナウイルス感染症の流行がおさまったとしても、私たちが健康を目指して生きていくうえでは、医療・健康情報と向き合う場面が必ず出てきます。例えば、自分自身や家族が病気になったときには、治療法について「期待する効果が得られるか」「副作用はどうか」「治療費はどのくらいか」など、情報をもとに解釈し、医療者とよく話し合って納得して選びたいもの。本書はそのような、よりよい意思決定につながるアドバイスを、具体例を挙げてまとめています。 -

治りにくい心の病
¥1,760それでも少しずつ良くなるためにあきらめず、少しでも良くなるような対応を考えるためのガイド。心の病が治りづらいのは特別なことではありません。
それでもあきらめず、少しでも良くなるような対応を考えるためのガイド。
よく見られる心の病について、なぜその病気・症状が改善しないのか考えられる理由を広く検討し、その原因・病気・症状ごとに、よりよい対処方法を一般の方向けにアドバイスする書籍です。改善しない理由を探ることから治癒への希望に結び付けることが狙いです。治りにくい理由として、診断の問題、治療方針の違い、投薬の違い、他の療法を考慮すべき、患者サイドの問題、併存する別の病気などが考えられます。どの病気であるにせよ、主治医との信頼関係を築くことが最重要となります。患者サイドも確かな知識を持って医療側と良いコミュニケーションを保つことが改善への道を開きます。
〔取り上げる病名〕統合失調症とその関連障害、うつ病、双極性障害、不安障害などのストレス性障害、摂食障害、パーソナリティ障害、各種の発達障害など。 -
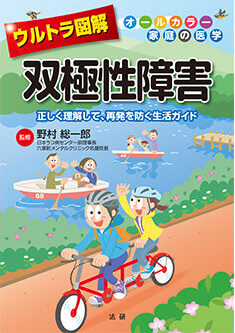
ウルトラ図解 双極性障害
¥1,650オールカラー図解シリーズ第24弾正しく理解して、再発を防ぐ生活ガイド再発しやすいが、きちんと治療を継続すれば、その人本来の生活を取り戻せる
気分が異常に高揚する「躁状態」と気分がどうしようもなく落ち込む「うつ状態」をくり返す双極性障害(旧名は躁うつ病)。薬物療法を中心とした治療をきちんと継続すれば、日常生活や社会生活に支障を来すことなく暮らすことが可能ですが、治療を止めると高い確率で再発してしまうのが特徴。また、うつ病と双極性障害を見極めるのは専門医でも難しいといわれており、躁状態を見逃したままうつ病の治療を続けているケースも多い。本書は双極性障害の概略、症状のでかたと診断、治療方法と生活での注意点などを豊富な図解を交えて詳述。本人・家族がともに病気を正しく理解し治療を継続するならば、双極性障害も恐れる病気ではなくなります。 -

そのふるえ・イップス 心因性ではありません
¥1,870不随意運動・ジストニアのしくみと治療原因不明、精神的なものといわれたふるえ、イップスを内科的、外科的なアプローチで治療するイップス、ふるえを心因性だからと諦める前に
ピッチャーがボールをうまく投げられない、ゴルフで打とうとするときに思わぬ動きをしてしまう、長年演奏してきた楽器を弾けなくなる、こうした症状は以前から知られ、イップスなどと呼ばれてきました。
そうしたイップスやふるえ、不随意運動で悩んでいる患者さんのなかには、脳神経と特定の動きが結びつき、その動作をしようとしたときにだけ不具合が起きてしまう人がいます。
局所性ジストニアなど、病気の本質が見極められ、正しく診断されれば有効な治療法がある病気もあります。
本書は局所性ジストニアを中心に、原因不明、心因性といわれていた病気のしくみや基礎知識、治療法をわかりやすく紹介します。 -
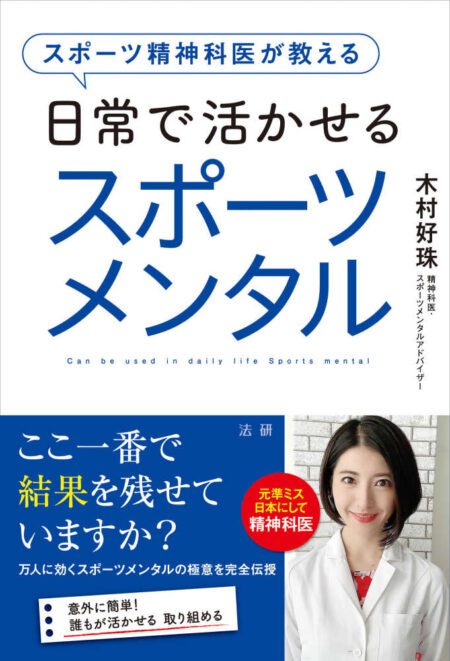
スポーツ精神科医が教える 日常で活かせるスポーツメンタル
¥1,650元準ミス日本の精神科医による初の著書!誰でも簡単に日常生活に取り入れられるスポーツメンタルの極意をやさしく、わかりやすく完全伝授かつて準ミス日本に輝いた経歴を持つ精神科医・木村好珠先生が、「大好きなサッカーに携わる仕事がしたい」という熱意をもって、早くから力を入れて取り組んできたスポーツメンタルのメソッドを詰め込んだ初の著書が誕生しました。パラリンピックの正式種目でもあるブラインドサッカー日本代表をはじめ、数々のチームでメンタルアドバイザーを務めてきた経験から語られるメンタル育成術は、万人に役立ち、日常生活で活かせるものばかりです。
「ここ一番で力を出せるメンタルを手に入れたい」――そんな想いを叶えるヒントがギュッと詰まった1冊です。 -

最新版 アトピー性皮膚炎をしっかり治す本
¥1,870正しい治療で症状を長引かせないつるつるきれいな肌を取り戻し、維持するアトピー性皮膚炎をコントロールする
アトピー性皮膚炎の寛解導入、寛解維持のための正しい治療法を専門医が詳しくわかりやすく解説。
乳幼児から成人までアトピー性皮膚炎を発症してしまったとき、症状が長引いてなかなか治らないとき、再発してしまったとき、「この治療法でよいのかな?」と思ったときに、ぜひ読んでほしい、レベルの高いエビデンスに基づいた本当に正しい治療法をわかりやすく詳しく解説する一冊。
患者さんが疑問に思うこと、迷うポイント、勘違いしやすい項目についてもしっかり説明。
再発を防ぐための日常生活でできる工夫についても豊富なイラストとともに紹介。 -

「ひざ痛」を治す!正しい歩き方
¥1,650ひざの痛みを軽くする、心も身体も元気になる「歩き方」一生自分の足で歩きたいひざの痛みを抱える多くのシニア世代への福音!
運動指導歴31年、のべ30万人の運動指導を行ってきた著者による
正しい歩き方の実践書。
●歩くとき、ひざにかかる「重さ」「衝撃」「ねじれ」に着目。それぞれの負荷から解放されるための体操を章別に紹介。
●それぞれの体操に5段階の難易度を表し、無理なく継続・達成していくための目安にできます。
本書により正しい歩き方を習得することで、ひざの治療や薬に頼らず「歩き方」を変えるだけでひざの痛みから解放され、健康な自分を取り戻すことができるようになります。
歩き方の見直しは、一生、元気に自分の足で歩き続けられ、日常生活のなかでの大きな効果を実感することにつながります。本書はそのためのバイブルを目指すものです。 -
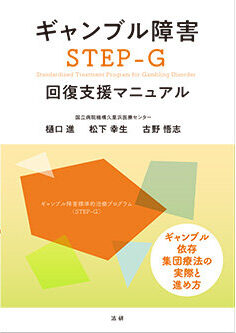
ギャンブル障害 STEP-G 回復支援マニュアル
¥2,750「ギャンブル依存症」を治療するには依存症集団療法の実際と進め方IR推進法によるカジノ合法化でギャンブル依存(ギャンブル障害)に注目が集まるようになりました。しかし、国内ではもともとギャンブルへのアクセスが容易で、以前からギャンブル障害に苦しむ患者や家族は少なくありませんでした。
ギャンブル障害は治療の必要な病気です。放っておくと進行してしまい金銭のトラブルを起こし人間関係や社会的信用に深刻な問題を生じてしまいます。また、家族が巻き込まれてしまうことも特徴の一つです。
本書はギャンブル障害の有効な治療法として認められる集団療法の標準プログラム(STEP-G)の考えに沿って、イネイブリングを断ち、回復を支援していくための方法を紹介します。プログラムの実施方法を教材イメージとともに紹介しながら、標準プログラムがどのように患者に働きかけ、変化をもたらしていくかも学ぶことができ、専門職として患者を支援する方にはもちろん、当事者、家族や身近な人にも役立ちます。