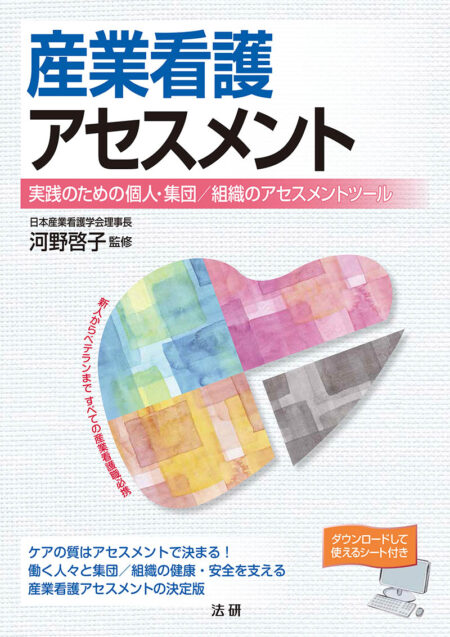-
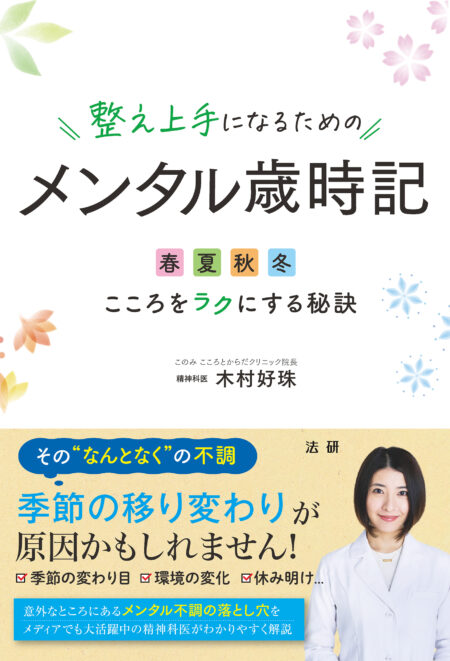
整え上手になるためのメンタル歳時記
¥1,870季節に合わせてメンタルを整えるコツを精神科医がわかりやすくナビゲート! オールシーズンこころが楽になります季節の変わり目は体調を崩しやすくなるもの。それは身体面に限られるわけではなく、精神面でもバランスを崩しやすくなるものです。また、季節の変わり目でなくとも、「梅雨のシーズンに体調を崩しやすい」「冬はどうしても気分が滅入ってしまう」など、特定のシーズンに不調を感じる人は意外と多いもの。この本は、そうした四季の移り変わりに伴って陥りやすいメンタルの不調を解説していきます。“なんとなくの不調=未病”のうちに自分で対策することで、オールシーズンこころを楽にできる――そんなヒントが詰まった1冊です。
【ポイント】移りゆく季節と心身の不調に着目
季節の変わり目に不調を覚える要因のひとつに、お馴染みの「自律神経」があげられます。本書でも頻出しますが、そこに「歳時記」が絡むところが本書のユニークなところ。また、「環境の変化というストレスへの適応」も、よくあるテーマですが、同様に「歳時記」というスパイスが加わるところが本書の魅力です。
【ピックアップ】例えばこんな見出しが載っています
・ゴールデンウイークはメンタルヘルスの落とし穴
・梅雨の天気がもたらす不調にご用心
・夏バテと勘違いしないで! 夏季うつ
・長期休暇から日常に戻るのがツラい…… -

足指ほぐし健康法
¥1,870足指が使えていないと全身に悪影響が及ぶ…大阪府富田林市の鍼灸師・柔道整復師の本田洋三先生は患者の足の状態を見続ける中、ほぼ全員が足指を使えていないこと、足が変形していることに気付きました。
【よく見かける足と足指の状態】
・足指が伸びていない
・足の親指が小指のほうへ曲がっている
・足裏にタコがある
・足指がくっついている
・足先の冷えやむくみがある
足は全身を支える重要な土台で全身の健康と深く連動しています。足の問題により重心のバランスが崩れると、腰痛やひざ痛、肩こりや頭痛など全身に悪影響が及びますが、『足指ほぐし健康法』で足指をほぐすと重心の偏りが正され、次第に不調が改善していきます。1日3分、『足指ほぐし』の習慣でいきいきとした毎日を!
基本の足指ほぐしは足指ぶらぶら、足指ずらし、足指ブリッジ、足指つかみ、足指スクワットの5種類。そして足指のデイリーケア法、歩き方と日常生活の注意点など、具体的な方法を豊富に紹介しました。足指ほぐし健康法は1日3分の習慣で足が変わり、体が変わり、人生が変わる画期的な方法です。健康な体で長生きするには日々のセルフケアが特に大切。一緒に足指ほぐしを始めませんか?
■本書の特徴■
●足指の状態がよくわかるチェック法
●高齢の読者でも取り組める安心・安全な内容
●直感的にわかる大きな文字と写真
●Web動画で動きの理解度アップ -
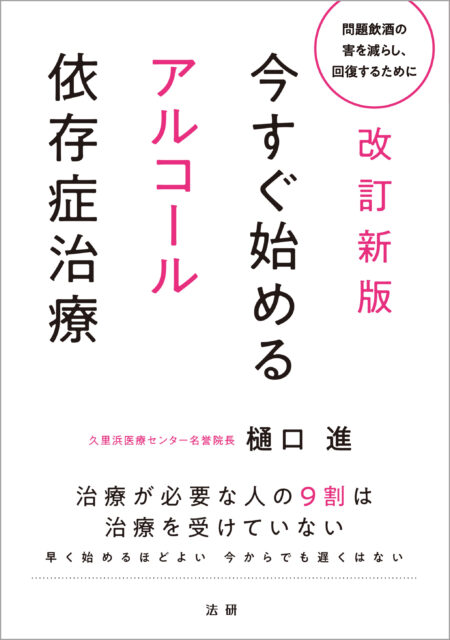
改訂新版 今すぐ始めるアルコール依存症治療
¥1,980アルコールから受ける害を少なくしていくために「今すぐ」アルコール依存症治療は、治療が必要な人の多くが受けていないことが問題です。放置していると進行し、酒量は増え、ますますコントロールがきかなくなります。本人の意思の力だけではコントロールすることはできません。また、家族など身近な人が叱ったり、止めようとしてもうまくいきません。健康や社会生活、また本人だけではなく身近な家族にも深刻な影響を与える事態になります。アルコール依存症は、飲酒運転や犯罪にも結びつきやすくなるリスクがあります。アルコールによるトラブルを少しでも経験した時点で(できればその前に)、対策を講じるようにすべきです。
一方で、近年、飲酒によるトラブルに対する社会の目は昔より厳しくなり、アルコールの害や治療に関する知識が広まったことにより、かつてより早期に治療を開始する人も増えています。また「断酒しかない」といわれていた治療も、ここへきて選択肢も増えてきており、それを助けるツールも登場しています。アルコール依存症の治療は難しく、時間のかかるものですが、その害を減らしていくことは今すぐに始めることができます。
本書は、2019年に刊行し大好評だった『今すぐ始めるアルコール依存症治療』をアップデート、最新の情報を収載した改訂新版。アルコール依存症が治療の必要な病気であることや、知っておくべき基礎知識、医療機関での治療、本人や家族にできる対処法などを詳しくわかりやすく紹介しています。 -
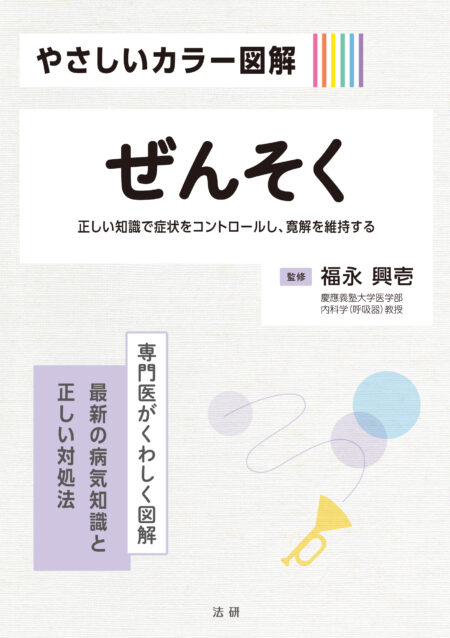
やさしいカラー図解 ぜんそく
¥1,870ぜんそくの症状をコントロールし、寛解の状態を維持するための必要な知識をオールカラー図解でわかりやすく解説ヒューヒュー・ゼイゼイという喘鳴や息切れ、息苦しさ、激しい咳などの症状がくり返し起こるぜんそく(喘息)は、呼吸時の空気の通り道である「気道」に生じる慢性の病気です。ぜんそくは発作をくり返すうちに悪化することがあり、進行すると日常生活にも影響します。
子どもの病気という印象がありますが、実際には成人の患者のほうが多く、中高年で発症する人もいます。
ぜんそくの患者さんは増えていますが、ぜんそくの治療法は進歩し、以前と比べてぜんそくで命を落とす人は減っています。
ぜんそくの悪化を防ぐためには、正しい知識と診断、対処法により、ぜんそく発作を適切にコントロールし、発作が起こりにくい状態「寛解」の状態を作り、維持することが大切です。
本書はオールカラーの豊富な図解を用いて、ぜんそくの基礎知識、アレルギー素因と環境要因などの発症リスク、小児ぜんそくと成人ぜんそく、検査、診断と治療、生活のなかでの工夫などについてやさしくわかりやすく解説します。治療ステップによる薬物治療や、アレルギー性鼻炎、COPD(慢性閉塞性肺疾患)などの合併症についても紹介します。 -
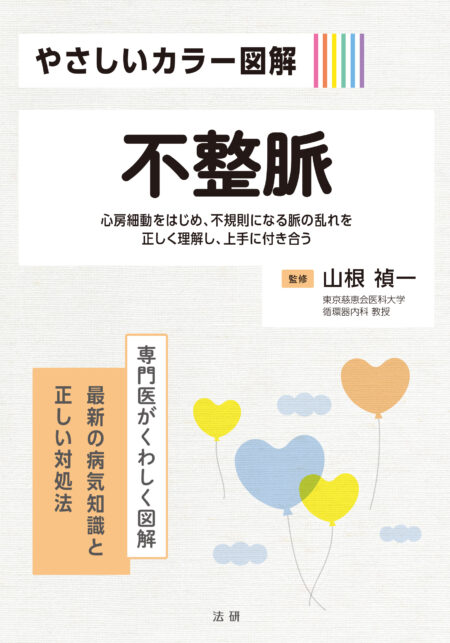
やさしいカラー図解 不整脈
¥1,870心房細動をはじめ、不規則になる脈の乱れを正しく理解し、上手に付き合う心臓のリズムが不規則になる不整脈。一言で不整脈と言っても、脈がはやくなる頻脈、遅くなる徐脈、急にとんだり抜けたり、大きくなったりするように感じられる期外収縮など、脈拍が乱れることの総称で、原因や症状はさまざまです。なかには注意が必要なもの、放置していると命に関わるものもあります。
本書は心房細動、心室細動、そのほかの不整脈について、基礎知識、原因、心電図などの検査、診断、治療が必要か、どのような治療を検討すべきか、悪化・再発させないための生活上の工夫などを、豊富なカラー図解とともにわかりやすく解説しています。保存治療、カテーテルアブレーションなどのカテーテル治療、ペースメーカーやICDなどの植込み型デバイスなど、それぞれの治療についても紹介しています。 -
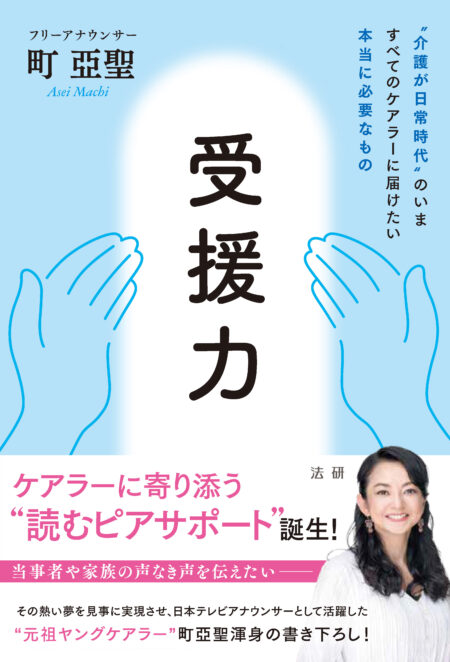
受援力
¥1,980■本書を一言で表せば“読むピアサポート”です。受援力(じゅえんりょく)とは、困ったときに誰かに助けを求めることができる力のこと。介護に直面したときに大切なのは、この「受援力」を発揮することです。
ある日突然、介護に直面すると、生活が一変してしまい、どうしていいかわからない状況に追い込まれ、精神的に追い詰められてしまう人も少なくありません。
介護はプロの力を借りることができますし、利用できるサービスもいろいろあります。すべてを自分で抱え込む必要はないのですが、「人に助けてもらう力」が弱いと、自分で何とかしようとしてしまいます。一時的なことなら、それでもいいかもしれませんが、介護は終わりが見えません。潰れてしまうことなく、「仕事や学業や家事」と「介護」を両立させながら乗り切っていくためには、周りにある資源を有効に活用し、頼っていくことが必要なのです。本書は元日本テレビのアナウンサーであり、 “元祖ヤングケアラー”とも呼ばれる著者・町亞聖さんが、介護に追い詰められてしまわないために、すべてのケアラーに伝えたいことを詰め込んだ渾身の書き下ろしです。
自身の介護経験を述べつつ、大変な状況に置かれているケアラーを慮りながら、「突然直面する介護への心構え」や「介護と仕事・学業との両立」など様々な切り口から介護生活を乗り切るためのヒントを熱く語ります。
著者自身が大変な介護を乗り越えたからこそ発せられる言葉には、抜群の説得力があり、心に響きます。すべてのケアラーの心にしっかりと寄り添ってくれるに違いない1冊です。=============
【本書「はじめに」より一部抜粋】
今から30年以上前にヤングケアラーの当事者の一人になった私も、弱音を吐くことや誰かを頼ることが今も苦手です。18歳の時から親を頼ることのできない環境に身を置いていたことが影響していると思います。私自身もまだまだ<受援力>が足りていないと痛感していますが、だからこそ「もしもあの時に助けてと言えたなら……」と過去の自分を振り返りながらこの本を書き進めていきたいと思います。自分の人生も大切にしながら介護を続けるためにはどうしたら良いのか? その鍵を握るのが<受援力>だと確信しています。この本が現在進行形で介護をしているみなさんが「助けて」と声を上げるきっかけになればと思いますし、ヤングケアラーだけではなく全てのケアラーのみなさんの今と未来を照らす小さな灯りになれば幸いです。 -
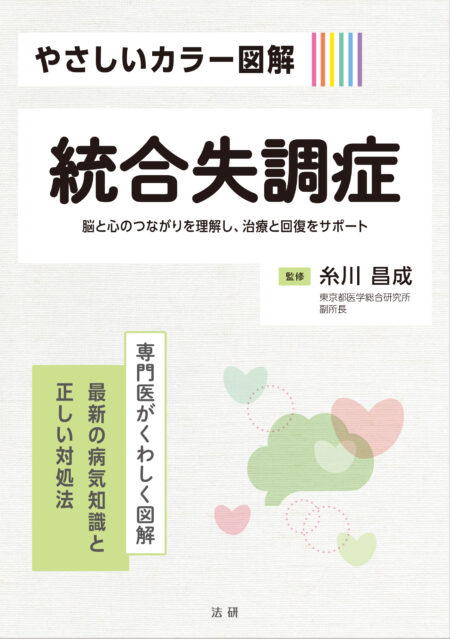
やさしいカラー図解 統合失調症
¥1,870身近でありながら誤解も多い統合失調症への理解を深め、
回復、症状のコントロールをサポートするための一冊考えや感情がうまくまとまらず、幻覚や妄想などの症状を伴う統合失調症は、100人に1人が発症するという推計もあり、身近な一方、誤解が多い病気でもあります。比較的若いうちに発症する人が多いという特徴もあり、そうした場合では進学、進路などへの影響も大きく、悩んだり心配している方も多いでしょう。
近年は、まだ不明な要素もありながら、治療方法等の進歩もあり、症状をコントロールしながら十分に社会復帰が可能な病気となっています。本書は理解が難しい部分もあるこの病気の原因・要因、症状、受診のポイント、治療とリハビリ、回復に向けた生活、支援制度などを、豊富なオールカラー図解でわかりやすく説明。家族をはじめとした周囲の人の対応が病状を左右するとされる統合失調症を、より深く理解して、患者さんとともにより良い人生を歩むための確かな情報を幅広く提供しています。 -
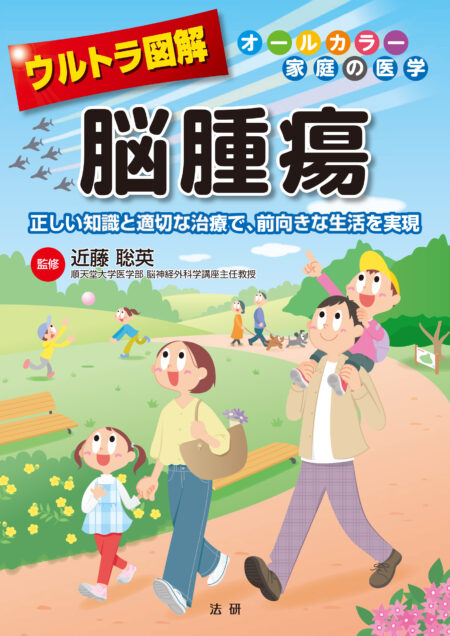
ウルトラ図解 脳腫瘍
¥1,980~正しい知識と適切な治療で、前向きな生活を実現~●病気に対する正しい知識を身につけ、不安や心配を少しでも解消するための1冊
頭蓋骨の中にできる腫瘍の総称である脳腫瘍は、細かく分類すると150種類以上にものぼります。脳を包む髄膜にできる「髄膜腫」、下垂体にできる「下垂体腺腫」など、約半数は手術で摘出すれば完治が可能な良性脳腫瘍です。「神経膠腫(グリオーマ)」など、脳そのものにできる腫瘍はほとんどが悪性脳腫瘍で、手術で完全に摘出するのは難しく、放射線療法や化学療法を組み合わせて治療を行います。近年は手術法・放射線療法も技術が進歩し、新薬の開発も進められており、あきらめず前向きに治療に取り組む意欲を持つことが大切です。よりよい治療を受けるためにも、病気に対する正しい知識を身につけましょう。 -
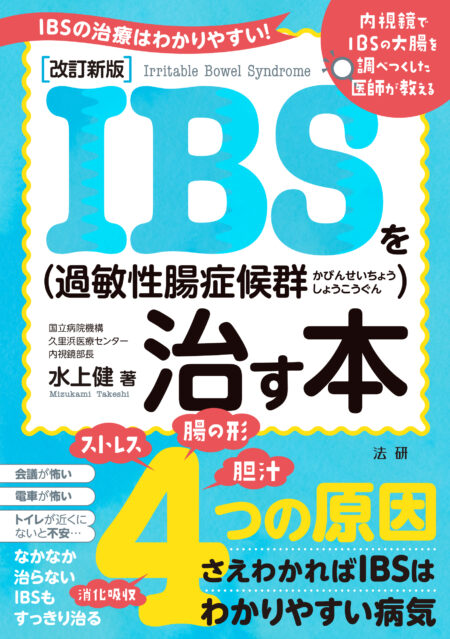
改訂新版 IBS(過敏性腸症候群)を治す本
¥1,8704つの原因さえわかればIBSはわかりやすい病気下痢・便秘などの症状に悩まされるIBS(過敏性腸症候群)。IBSの患者さんは、5人に1人ともいわれています。ストレスが症状を起こすきっかけとなることも多いため、心因性の病気と考えられていることも多く、患者さんが多い割には誤解の多い病気でもあります。実はIBSは4つの病態に分けられ、患者さんご自身がどれに当てはまるか知り、正しい対処をすればコントロールの容易な病気です。
本書は、2016年に刊行し大好評だった『IBS(過敏性腸症候群)を治す本』をアップデート、最新の情報を収載した改訂新版。大腸内視鏡検査のエキスパートで、患者に負担の少ない検査法である「浸水法」を発表した著者による、IBSの正しい知識と、治療法をわかりやすく解説する本です。テレビ番組で紹介され反響の大きかった腸のマッサージ法など、患者さんが自宅でも行える対処法や、治療の最新情報も紹介しています。また、正しい対処法を見つけてIBSを卒業していった患者さんの体験談も収載しています。 -
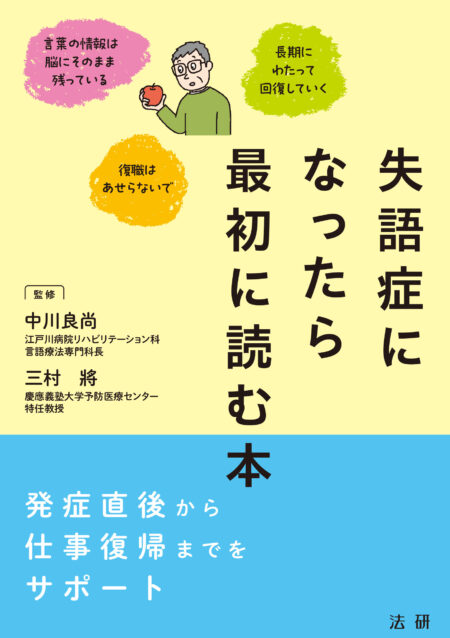
失語症になったら最初に読む本
¥1,980■失語症の基本から仕事復帰までの情報を網羅言語障害の一つで、コミュニケーション能力が低下する「失語症」。失語症は主に脳卒中などを原因に起こりますが、失語症になると本人や家族は大きなストレスを抱えることになります。失語症になった直後から知っておきたいことや、検査、治療、リハビリテーション、家族と患者のコミュニケーションの仕方、失語症患者が使える福祉サービス、仕事復帰に向けての準備の仕方、失語症経験者の体験談などの情報を網羅しました。失語症患者と家族が知りたい情報をまとめた一冊です。
-
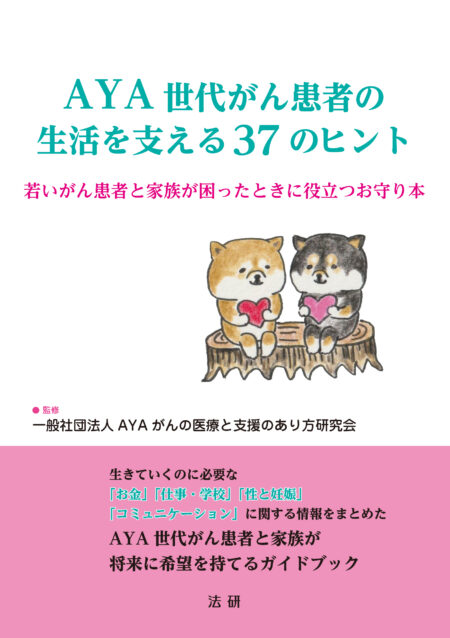
AYA世代がん患者の生活を支える37のヒント
¥2,420■AYA世代がん患者の特有の悩みを解決AYA世代は、学業、就職、結婚、妊娠・出産など大きな転換期を迎える時期です。このような時期にがんと診断されると、特にAYA世代は治療による体の負担や副作用によって妊娠する力に影響が出たり、学業の継続やキャリアの形成等で困難が生じたりするなど、世代特有の生きにくさを抱えることが少なくありません。またAYA世代は希少がんにかかることも多く、成人がんに比べ情報が少なくとても困っている状況にあります。同年代のがん患者が少ないため周囲と悩みを共有できず、不安を抱く人も少なくありません。
本書は、AYA世代のがん患者へのサバイバーシップ支援に力を注いでいる一般社団法人AYAがんの医療と支援のあり方研究会にご協力いただき、AYA世代でがんと診断された人とその家族に向けて、退院後の生活上の困りごとや悩みの解決に役立つと思われる情報を37のヒントにまとめました。AYA世代のがん患者と家族が将来に希望を持てるガイドブックとなっています。★AYA(アヤ)世代とは:Adolescent and Young Adult(思春期・若年成人)の頭文字をとったもので、主に、思春期(15歳~)から39歳までの世代を指しています。