-
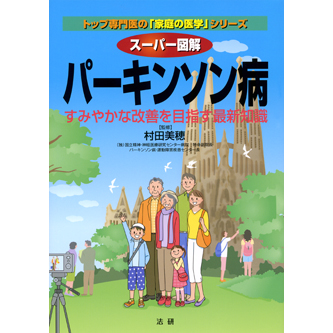
スーパー図解 パーキンソン病
¥1,540トップ専門医の「家庭の医学」シリーズすみやかな改善を目指す最新知識増えている“パーキンソン病”
日本のパーキンソン病患者は年々増加しており、2011年の厚生労働省の患者調査では、全国に14万1千人。
70歳以上の100人に1人程度の割合で発症するといわれています。
また、患者数は50歳代から60歳代にかけて増加し、日本では女性に多くみられることも特徴です。
パーキンソン病は脳内の神経伝達物質の分泌異常を原因として“ふるえ”“筋肉のこわばり”“動作が遅くなる”“姿勢が保ちにくくなる”などの身体的な症状が現れる病気です。
かつては回復が難しい病気でしたが、現在は薬物療法の進歩に伴いリハビリテーションとの組み合わせによって、かなり症状を軽減できるまでになっています。
本書は超高齢化社会を迎え、ますます発症頻度が上昇しているパーキンソン病の原因、検査、診断、治療法など、図解を駆使し、わかりやすく解説します。 -
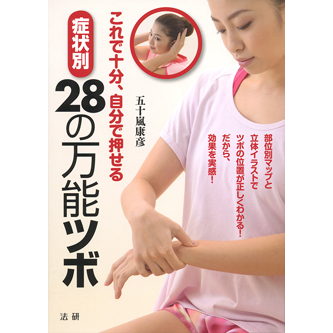
症状別 28の万能ツボ
¥1,430これだけ知っておけば…の厳選28ツボこれで十分、自分で押せる部位別のマップと、立体イラストでツボの位置が正しくわかる!
だから効果を実感!
私たちの体には、無数のツボが分布しています。その一つひとつに効果がありますが、すべてを覚えるのは困難です。
数あるツボのなかで、これだけ知っておけばたいていの症状に対応可能なツボを28個厳選し、体の部位別にまとめました。
だれでも簡単にできる指圧法のポイントもわかりやすく解説。 -
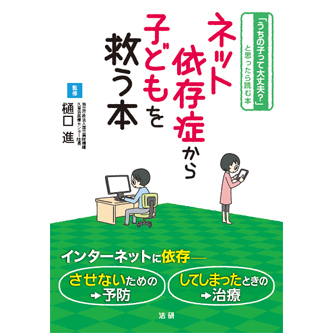
ネット依存症から子どもを救う本
¥1,540子どもがインターネットに依存してしまったときどうする?「うちの子って大丈夫?」と思ったら読む本PC、スマホが普及するとともに、社会問題となっているネット依存症。
中高生など、子どもにも急増しています。
ネット依存症は、オンラインゲームやSNSなどネットの使用状況が単なるネット、ゲーム好きの域を超えて、不登校やひきこもりなど、生活に支障が出るような状況になっている状態です。
この状態が続くと、意欲の減退、言動の変化、さらには健康状態や成長にも影響することがあります。
本書はネットと接する機会の増えてきたお子様を持つ保護者の方向けに、わが子をネット依存症にさせない、またネット依存状態に陥っている子を救い出す方法を事例を紹介しながら解説します。 -
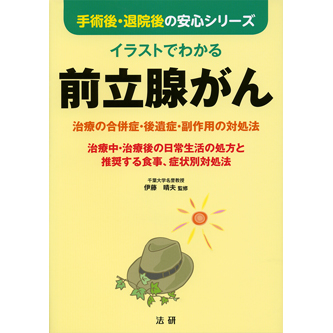
イラストでわかる 前立腺がん(手術後・退院後の安心シリーズ)
¥1,540治療中・治療後の日常生活の処方と推奨する食事、症状別対処法治療の合併症・後遺症・副作用の対処法◆本書の特長
1.前立腺がんの治療後・治療中の患者さんが対象
前立腺の治療は「手術」「放射線療法」「ホルモン療法」の3つが主なものです。どの治療でも生存率が高く、自宅に戻り再発を予防しながら暮らし続ける人がほとんどです。そんな患者さんに、日常生活で気をつけたいことや推奨する食事などをアドバイスします。
2.治療の合併症・後遺症・副作用の対処法をアドバイス
手術の後遺症である「尿失禁」「勃起不全」「リンパ浮腫」や放射線・ホルモン療法の副作用である「排尿・排便障害」、「ホットフラッシュ」などへの対処のしかたをアドバイスします。
3.前立腺がんにかかったときの費用や公的支援制度をアドバイス
前立腺がんの医療費やそれ以外にかかる費用。かかった費用がある程度戻ってくる公的支援制度や民間の生命保険について最新の情報を提供します。 -
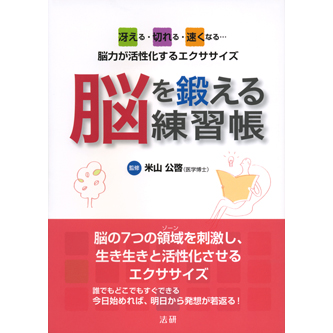
脳を鍛える練習帳
¥1,430脳の7つの領域(ゾーン)を刺激し、生き生きと活性化させるエクササイズ~冴える・切れる・早まる… 脳力が活性化するエクササイズ~超高齢化社会を迎え、近年認知症患者の増加が著しい。
そうした状況を踏まえ、厚生労働省は平成25年度医療計画で各自治体に向け、認知症を含む精神疾患患者の対策ガイドラインを作成した。
ことさら認知症を持ち出すまでもなく、中高年で“もの忘れ”など、脳の“ぼけ”症状でお悩みの方は少なくないだろう。
本書はそうしたぼけでお悩みの方を対象とした、脳を活性化するための“おもしろテキスト”である。
連合野、言語野など脳の各部位を刺激し、全体として脳内ネットワークを生き生きと回復させるエクササイズを、医学的な背景をまじえ、楽しく紹介する。 -
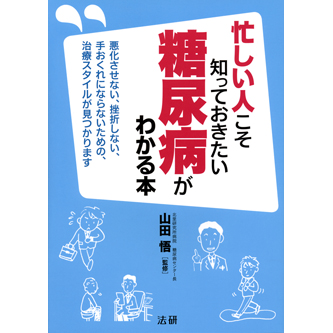
忙しい人こそ知っておきたい 糖尿病がわかる本
¥1,650悪化しない、挫折しない手おくれにならないための、治療スタイル糖尿病で最も怖いのは合併症です。合併症は適切な治療で防ぐことができます。しかし、多くの糖尿病患者が健康診断や医師の指導を実行できず、治療をあきらめたり、病気を放置したりしてしまい、合併症を起こし、悪化させてしまっています。
◆本書の特長◆糖尿病と診断された方の中でも仕事や介護、育児などで忙しい人を対象に、糖尿病の治療生活を医学的知識と患者さんの体験談をもとに詳しく解説。マンガと図解も多用して気軽に読めます。治療の王道である標準治療はしっかりおさえつつ、糖質制限食など多数の選択肢の実際を知ることができます。病気の知識はもちろん、治療がどのように行われるか、治療生活がどのようなものか、患者さんの苦労や悩み、そしてその克服法がわかります。どんなに忙しくても継続できる治療スタイルを提案します。 -
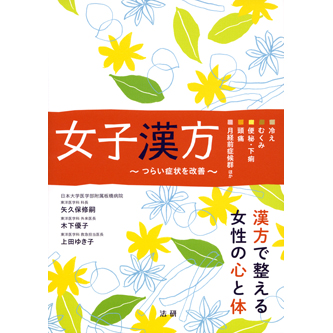
女子漢方
¥1,430漢方で整える女性の心と体つらい症状を改善健診で異常なし。
でも、その自覚症状が漢方では重要です
具体的な病気ではないけれど、不快な症状に悩んでいる…。
漢方では、その状態を「未病」と言い、病気になる前の重要なサインと捉えて、この段階から治療を始めます。
女性は生理周期や、自律神経系など小さな不調を来しやすく、こうした症状に漢方が向いています。
本書は女性の不調を解消し、より健やかにいきいきと生活を送ってもらうために、漢方の考え方を紹介し、医療機関での漢方を用いた治療、漢方薬、また食事法などを解説します。
◆本書の特長◆
●女性特有の症状を「漢方」と「西洋医学」の点からやさしく解説し、それぞれおすすめの漢方の「処方」「過ごし方」「おすすめの食材とおかず」を紹介
●季節の変わり目に起こりやすい不調と養生法、女性のライフステージで起こりやすい不調と養生法を紹介
●漢方の基本をやさしい言葉で解説 -
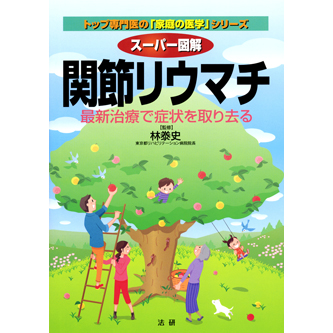
スーパー図解 関節リウマチ
¥1,540トップ専門医の「家庭の医学」シリーズ最新治療で症状を取り去るかつて“関節リウマチ”は、鎮痛薬や炎症を抑える薬などの対症療法的な治療しかなかったため、“一生付き合っていく病気”でした。
しかし、90年後半から画期的な治療薬が続々と登場し、現在では発見が遅れなければ、関節の痛みや症状がなく日常生活も問題なく過ごせる「寛解(かんかい)」に至ることも難しくありません。
本書は激変した関節リウマチ治療の最新情報を、図解を用いてわかりやすく解説。併せて、リハビリや日常生活の知識も網羅し、関節リウマチの患者さまはもちろん、その家族、予備軍の方必読の一冊です。 -
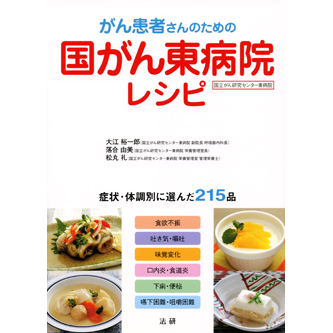
がん患者さんのための国がん東病院レシピ
¥2,200おいしいレシピ214品掲載!国立がん研究センター東病院の医師・管理栄養士と患者さんがつくった日本では、生涯のうちに2人に1人ががんになるとされ、現実に3人に1人ががんで亡くなっています。
がん患者さんにとって、治療効果を高め、がんと闘う体力を維持するためには「食事」はとても大切な要素です。
しかし、がん予防の食生活は多く研究されていますが、闘病中のがん患者さんの食生活に参考となるものは大変少ない、というのが現状です。
実際、多くのがん患者さんは、抗がん薬や放射線治療により、食欲不振や味覚変化、下痢・便秘、吐き気などの副作用の影響から食事が十分にとれず、体力低下や栄養不足に悩んでいます。
そこで、千葉県柏市の「国立がん研究センター東病院」では、副作用を抱えるがん患者さんの要望にきめ細かく対応し、そのなかで生まれた調理法やレシピを料理教室で患者さんたちに身につけてもらう試みを実践してきました。
本書では、その料理教室で実際に作って好評だった214品を紹介。
副作用についての解説や患者さんの悩みに答えるQ&Aなど、がん患者さんと家族のための「食事」情報を1冊にまとめました。 -
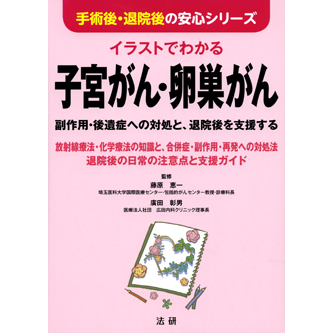
イラストでわかる 子宮がん・卵巣がん(手術後・退院後の安心シリーズ)
¥1,540放射線療法・化学療法の知識と、合併症・副作用・再発への対処法副作用・後遺症への対処と、退院後を支援する女性では乳がんとともに心配される「婦人科がん」。
子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん、それぞれ違う「がん」ですが、退院後の生活のポイントは共通する部分が多くみられます。
がんや手術による合併症や化学療法などの副作用は、婦人科がんの患者さん共通の悩みです。こうしたトラブルの予防と、起きたときの対処法、さらに充実した日々を送るための食事の摂り方、運動のしかた、性生活、心の悩みへの対処法などを解説します。 -
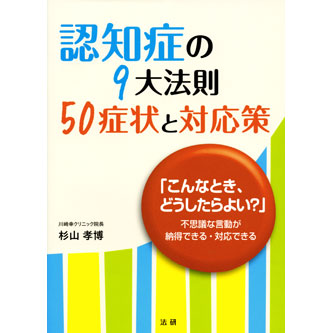
認知症の9大法則 50症状と対応策
¥1,540「こんなとき、どうしたらよい?」不思議な言動が納得できる・対応できる認知症の患者数は300万人を超え、政府の予測を大幅に上回るペースで増加しています。今後、自分が認知症にならなくても、家族や周囲の人が認知症になる可能性は十分にあります。
「認知症と診断されたらどうしたらよいのか?」「仕事はいつまで続けられるのか?」「具体的に何をすればよいのか?」「どのように進行、変化していくのか」などの事例と対応策を紹介。
過食や暴言など、不思議に感じられる認知症の症状は、実はある程度、類型化できます。その特性をまとめたものが、「認知症をよく理解するための9大法則」で、さまざまな症状はこの法則にそって説明することができます。
本書では、認知症の代表的な症状50に対する対応策を解説しています。
・解説するのは、30年前から在宅介護に取り組み、「認知症の人と家族の会」の副代表を務める杉山孝博先生。長年の経験をもとに、認知症症状が現れているときの、認知症の人の気持ちや状態についても、9大法則をもとにわかりやすく説明しています。
・「車の運転はいつまでできますか?」など、シーンごとに必要なところだけを調べられる、見開き完結型の知りたいことがさっとわかるレイアウト。 -
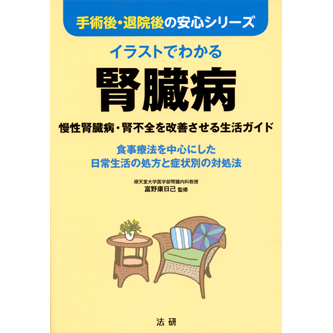
イラストでわかる腎臓病(手術後・退院後の安心シリーズ)
¥1,540慢性腎臓病・腎不全を改善させる生活ガイド食事療法を中心にした、日常生活の処方と症状別の対処法慢性腎臓病の方、透析治療を受けている方のための食事療法を中心にした日常生活の処方と支援ガイド
本書は、慢性腎臓病と診断された患者さんのための「透析を受けないようにするための自己管理法」そして、透析療法を受けるようになった患者さんのための「スムーズに治療を受け明るく過ごすための自己管理法」を紹介します。