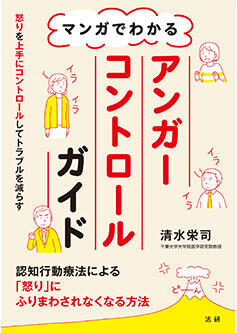-
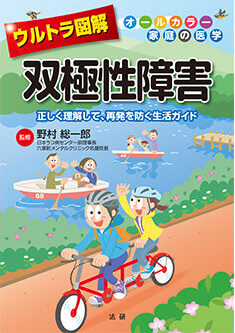
ウルトラ図解 双極性障害
¥1,650オールカラー図解シリーズ第24弾正しく理解して、再発を防ぐ生活ガイド再発しやすいが、きちんと治療を継続すれば、その人本来の生活を取り戻せる
気分が異常に高揚する「躁状態」と気分がどうしようもなく落ち込む「うつ状態」をくり返す双極性障害(旧名は躁うつ病)。薬物療法を中心とした治療をきちんと継続すれば、日常生活や社会生活に支障を来すことなく暮らすことが可能ですが、治療を止めると高い確率で再発してしまうのが特徴。また、うつ病と双極性障害を見極めるのは専門医でも難しいといわれており、躁状態を見逃したままうつ病の治療を続けているケースも多い。本書は双極性障害の概略、症状のでかたと診断、治療方法と生活での注意点などを豊富な図解を交えて詳述。本人・家族がともに病気を正しく理解し治療を継続するならば、双極性障害も恐れる病気ではなくなります。 -
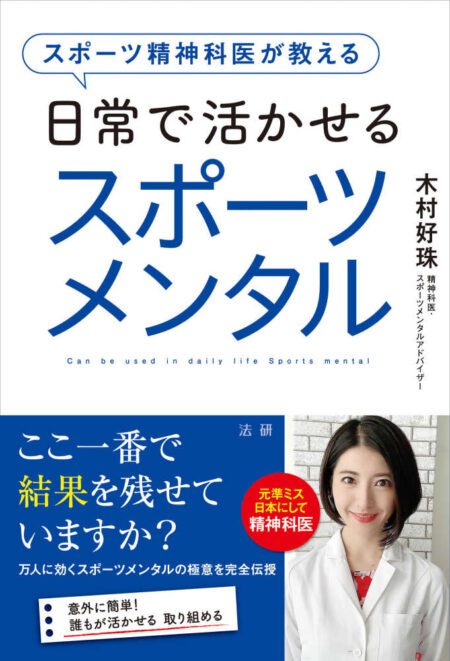
スポーツ精神科医が教える 日常で活かせるスポーツメンタル
¥1,650元準ミス日本の精神科医による初の著書!誰でも簡単に日常生活に取り入れられるスポーツメンタルの極意をやさしく、わかりやすく完全伝授かつて準ミス日本に輝いた経歴を持つ精神科医・木村好珠先生が、「大好きなサッカーに携わる仕事がしたい」という熱意をもって、早くから力を入れて取り組んできたスポーツメンタルのメソッドを詰め込んだ初の著書が誕生しました。パラリンピックの正式種目でもあるブラインドサッカー日本代表をはじめ、数々のチームでメンタルアドバイザーを務めてきた経験から語られるメンタル育成術は、万人に役立ち、日常生活で活かせるものばかりです。
「ここ一番で力を出せるメンタルを手に入れたい」――そんな想いを叶えるヒントがギュッと詰まった1冊です。 -
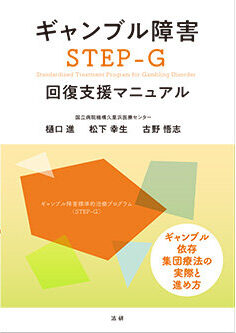
ギャンブル障害 STEP-G 回復支援マニュアル
¥2,750「ギャンブル依存症」を治療するには依存症集団療法の実際と進め方IR推進法によるカジノ合法化でギャンブル依存(ギャンブル障害)に注目が集まるようになりました。しかし、国内ではもともとギャンブルへのアクセスが容易で、以前からギャンブル障害に苦しむ患者や家族は少なくありませんでした。
ギャンブル障害は治療の必要な病気です。放っておくと進行してしまい金銭のトラブルを起こし人間関係や社会的信用に深刻な問題を生じてしまいます。また、家族が巻き込まれてしまうことも特徴の一つです。
本書はギャンブル障害の有効な治療法として認められる集団療法の標準プログラム(STEP-G)の考えに沿って、イネイブリングを断ち、回復を支援していくための方法を紹介します。プログラムの実施方法を教材イメージとともに紹介しながら、標準プログラムがどのように患者に働きかけ、変化をもたらしていくかも学ぶことができ、専門職として患者を支援する方にはもちろん、当事者、家族や身近な人にも役立ちます。 -
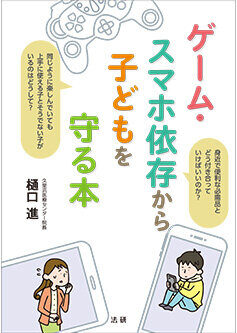
ゲーム・スマホ依存から子どもを守る本
¥1,760専門医が教える、ゲーム・スマホ依存への対処法、予防法身近で便利な必需品とどう付き合っていけばいいのか?同じように楽しんでいても上手に使える子とそうでない子がいるのはどうして?
WHO(世界保健機関)の国際疾病分類最新版ICD-11でゲームへの依存が病名として認められたことで注目を集めるようになったゲーム依存。近年はスマホでのゲームに依存する人が増え、より問題が複雑になってきています。
ゲーム・スマホ使用はそれ自体を止めることがとても難しいという点がほかの依存との違いです。
本書はゲーム・スマホ依存の基礎知識とともに、ゲーム・スマホ使用を適切にコントロールするためにご家庭でできること、依存状態から回復するための対処法を解説します。 -
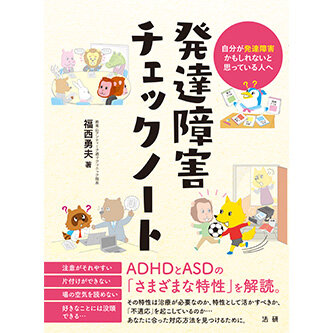
発達障害チェックノート
¥1,760自分が発達障害かもしれないと思っている人へADHD、ASDに見られるさまざまな特性を多く取り上げ、対応方法を見つけるためのチェックノート注意がそれやすい、依頼や指示を忘れる、片付けができない、場の空気を読めない、好きなことには没頭できる…などなど。代表的な発達障害である注意欠如多動性障害(ADHD)と自閉症スペクトラム障害(ASD)に関して、よく見られる特性をもっていた場合、その特性は治療が必要なのか、どの程度の「不適応」を起こしているのか、または特性として活かすべきなのか…。本書はあなたに合った対応方法を見つけるために数多くのケースを取り上げ、その意味について解説していきます。発達障害のさまざまな特性への対応を助けるガイドブックです。
-
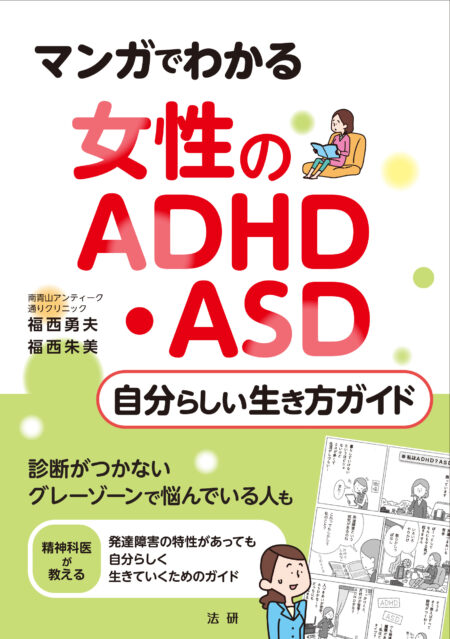
マンガでわかる 女性のADHD・ASD 自分らしい生き方ガイド
¥1,870診断がつかない「グレーゾーン」で悩んでいる人にも役立つ精神科医が教える 発達障害の特性があっても自分らしく生きていくためのガイド発達障害といっても、悩みや置かれている環境は人それぞれ。
発達障害と診断を受けた、もしくは発達障害の特性に悩む女性向けに、ご自身の特性を理解し少しでも生きづらさを改善していくための考え方のヒントをマンガでわかりやすく解説する本。
ADHD(注意欠如・多動性障害)やASD(自閉症スペクトラム)などの発達障害の特性を持ったり、特性を持つが診断はつかないグレーゾーンや診断ボーダーライン上にあると悩んでいる女性に向けて、発達障害の基礎知識や医療機関での治療法を易しい説明とマンガで紹介。豊富な事例が、生活コントロールのためのヒントになる。
発達障害の特性を持っていても、特性を個性の一つと考えて、自分らしく生きていくための本。 -
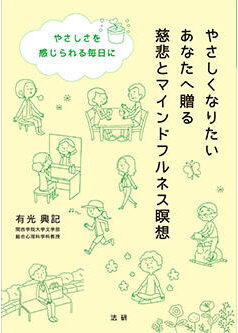
やさしくなりたいあなたへ贈る 慈悲とマインドフルネス瞑想
¥1,870やさしさを感じられる毎日に話題のマインドフルネス瞑想最新刊慈悲の瞑想とマインドフルネス瞑想の組み合わせで自分の中にあるやさしさに気づく
ストレス社会ともいわれる現代社会において、悩みやストレスの解消につながる瞑想法として注目されているマインドフルネス瞑想。その効果を一層高めるのが、慈しみの気持ちをもちながら、あらゆるものの幸せを願う「慈悲の瞑想」と組み合わせて行うことです。慈悲の瞑想は、肯定的な感情を向上させることができ、2つの瞑想を組み合わせることで、自分の中にあるやさしさを感じることができるようになります。
本書では、慈悲の瞑想とマインドフルネス瞑想の基本的な考え方を、事例をまじえて紹介するとともに、10のステップでその実践方法を紹介していきます。 -
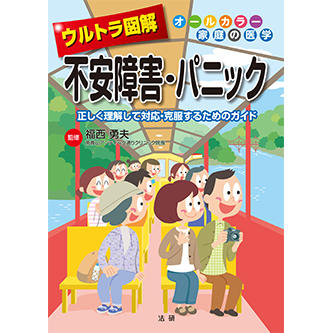
ウルトラ図解 不安障害・パニック
¥1,650オールカラー図解シリーズ正しく理解して対応・克服するためのガイド自分ではどうすることもできない「異常な不安」は、専門医への受診が必要です。
潜在的な患者数ではうつ病を上回るとも言われている「不安障害」。代表的なパニック障害をはじめ、広場恐怖症、社交不安障害、強迫性障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)など、さまざまな形が知られています。本書は「コントロールできない病的な不安」や「パニック発作」、「くりかえす強迫行動」などに悩む患者やその家族向けに、正しい診断を受けた上で治療を進めるために必要な知識を、具体的かつわかりやすく解説。間違えやすい他の病気や併発しやすい病気・症状の説明なども含めて、不安障害の全体像を解き明かし、快復までの道のりをガイドします。 -
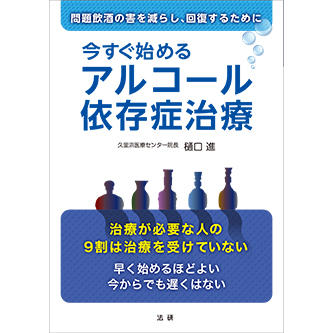
今すぐ始めるアルコール依存症治療
¥1,760変わる、アルコール依存症治療問題飲酒の害を減らし、回復するために早く始めるほどよい
今からでも遅くはない
アルコール依存症は、本人の努力や家族だけの力では回復することが難しく、適切な対処をしないと進行し、健康や社会生活に大きな影響を与えます。問題のある飲酒者は日本国内に100万人以上いるといわれていますが、専門機関で治療を受けているのはごく少数です。
ここへきてアルコール依存症の治療は転機を迎えています。
より早い段階から治療を始める人が増えていること、また従来、酒をやめる「断酒」しか治療法はないといわれていましたが、「減酒」という新しい治療アプローチも選択肢として増えてきたこと、また新薬などそれを助けるツールも登場していることなどが注目されています。それを支持する診断・治療ガイドラインも作成されました。また、すでに進行したアルコール依存症の人でも治療を行うことによって、健康状態は大きく改善します。
飲酒による問題のある人は誰でも、今すぐ治療を始めましょう。 -
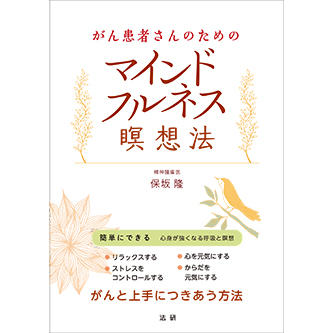
がん患者さんのための マインドフルネス瞑想法
¥1,760簡単にできる 心身が強くなる呼吸と瞑想がんと上手につきあうために精神腫瘍医が教える 心を整える方法
がんは二人に一人がかかる病気です。現在は医療技術も進み、がんと診断されても、そうでない人と同じくらい長く生きる人も増えてきています。しかし、個々人の患者さんの心に与える衝撃が大きいことは間違いありません。がん患者さんは心に不調を抱えてしまうことが多く、また、心の不調が治療やQOL(生活の質)に影響してしまうことも少なくありません。
心の状態がよいと、治療や病気の予後にもよい影響があります。
本書では、がん患者さんとご家族の心のケアを専門とする精神腫瘍医である著者が、がんとともに生きるための心のあり方や死生観、脳と免疫の関係をやさしく解説し、ご自宅で簡単に行えるマインドフルネス瞑想法でストレスをやわらげ、リラックスした状態を作る方法を紹介します。 -
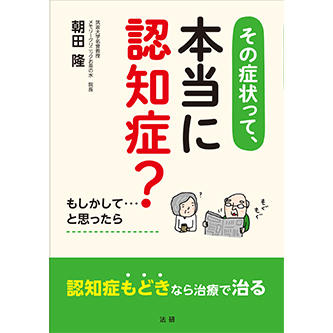
その症状って、本当に認知症?
¥1,650もしかして、と思ったら・・・認知症と症状が似た治療可能な病気認知症と診断されたが、実は認知症ではなかった!?
認知症は患者数が多いので、身近な高齢者にもの忘れが増えたり、以前と比べて変わった様子を見ると「認知症かな?」と考えがちです。しかし、「認知症のように見えて認知症ではない、治療可能な病気」はたくさんあります。医師から「認知症」と診断された例でも、後から違ったとわかることもあります。適切な治療をすることで認知機能が回復する例も少なくないのです。また高齢者の認知機能は、環境や体調などからも影響を受けやすいものです。本書は認知症と間違えやすい病気、高齢者の認知機能を低下させる要因を解説し、認知機能を回復する可能性があれば適切な対処を行い、いきいきと暮らすための対処法や工夫を紹介します。