-
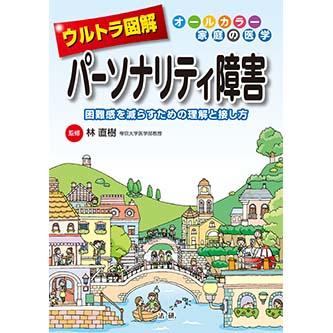
ウルトラ図解 パーソナリティ障害
¥1,650生きづらさ・苦しみを減らすための理解と接し方オールカラー家庭の医学パーソナリティの偏りからくるトラブルを減らすために
パーソナリティ障害は、人としての性格・特徴(パーソナリティ)の偏りが極端になってしまって、さまざまな問題が生じるようになるという精神疾患です。独特の思考や、それに基づいた行動のために周囲の人とトラブルを起こしたり、本人も困っていることがあります。
パーソナリティ障害は、タイプも原因もさまざまです。本書はこのパーソナリティ障害の正しい知識と10のタイプそれぞれの説明、対処法を豊富なカラー図解とともにわかりやすく解説します。 -
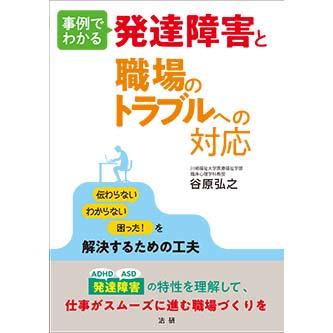
事例でわかる 発達障害と職場のトラブルへの対応
¥1,870伝わらない、わからない、困った!を解決するための工夫発達障害の特性を理解して、仕事がスムーズに進む職場づくりを発達障害の人もそうでない人も安心して働ける職場環境を
発達障害の人はその特性から、職場でトラブルを起こしたり、周囲を戸惑わせてしまうことがあります。しかし発達障害ゆえに、自分だけでは解決できず困っていることも多いものです。
長年、職場のメンタルヘルスに携わってきた著者が、発達障害の特性を持つ人への適切な支援・働きかけにより、トラブルが減り、本人だけではなく周りの人もより安心して働ける職場づくりにつながった事例を数多く紹介します。
発達障害を持つ人、また同じ職場で働く人双方の理解を深める一冊です。 -
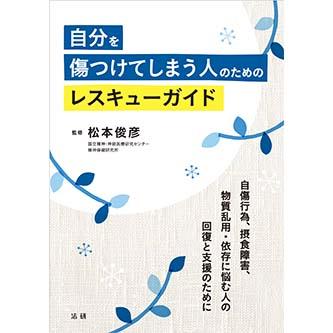
自分を傷つけてしまう人のためのレスキューガイド
¥1,760自傷行為、摂食障害、物質乱用・依存に悩む人へ自傷行為、摂食障害、物質乱用・依存はつながっている自分で直接自分を傷つける自傷行為と、目的はそうではなくても間接的に健康を害してしまう摂食障害、物質乱用・依存は、それぞれ別の行為のように見えますが、実はつながっています。
こうした自分を傷つけてしまう行為をやめられない人、そのご家族、支援者に向けて、知識と回復のための考え方をわかりやすくかつ具体的に解説します。
・誤解の多い自傷行為が理解できる
・心に抱えた生きづらさと共存するために
・傷つけなくても済むためのスキルを身につける -
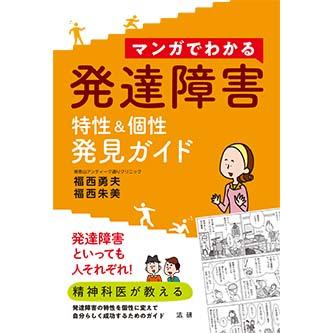
マンガでわかる 発達障害 特性&個性 発見ガイド
¥1,760発達障害といっても人それぞれ!精神科医が教える 発達障害の特性を個性に変えて自分らしく成功するためのガイド以前に比べるとADHD(注意欠如・多動性障害)や、アスペルガー症候群、ASD(自閉症スペクトラム障害)といった言葉はだいぶ知られるようになりました。これからはこうした発達障害を抱える人が、実は非常に多く、またそれぞれ個人差が大きいということも、もっと知られるべきでしょう。
本書では、発達障害を持つ人、発達障害の傾向がある人が、自身の特性を見極め、個性を活かして、いきいきと自分らしく生活していくための考え方のヒントを、マンガを多用してわかりやすく紹介しています。 -
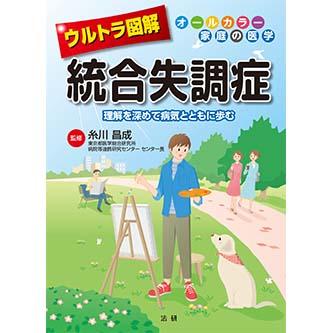
ウルトラ図解 統合失調症
¥1,650オールカラー 家庭の医学決して珍しくない統合失調症を確かに理解して、治療と回復をサポート100人に1人が発症するとされる統合失調症は代表的な心の病気で、若いうちに発症する人が多いのが特徴。
最近の治療方法の進歩もあり、十分に社会復帰が可能な病気となっています。本書は理解が難しい部分もあるこの病気の原因・要因、症状、受診のポイント、治療とリハビリ、回復に向けた生活、支援制度などを、豊富な図解でわかりやすく説明。家族をはじめとした周囲の人の対応が病状を左右するとされる統合失調症を、より深く理解して、患者さんとともにより良い人生を歩むための確かな情報を、幅広く提供しています。 -
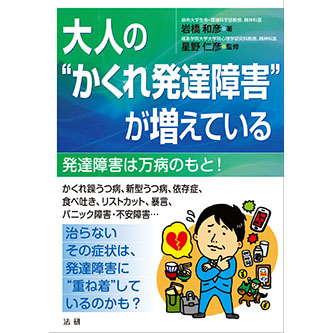
大人の“かくれ発達障害”が増えている
¥1,760発達障害は万病のもと!治らないその症状は、発達障害に“重ね着”しているのかも?かくれ躁うつ病、新型うつ病、様々な依存症、パニック障害・不安障害……。
治らないその症状は、発達障害に“重ね着”しているのかも?
最近、増えているといわれる「大人の発達障害」。その特徴の一つは思春期以降に様々な二次障害・合併症をおこし、元来の発達障害が見えにくくなってくること。
新型うつ病、躁うつ病、アルコール・薬物・ギャンブル依存などの精神障害、ストーカー、DV、いじめ・虐待などの問題行動の陰には“発達障害がかくれている”と著者は主張します。
これらの「重ね着症候群」では元の発達障害という“素肌”のケアをしない限り、見かけの上着の障害はなかなか治りません。
本書は、どのようなケースで大人の発達障害を疑い、より正しい診断、治療を受け、さらに生活をより楽にするための対応など、患者とその家族が必要とする知識(とくに生活指導と薬物治療)を一冊にまとめています。 -
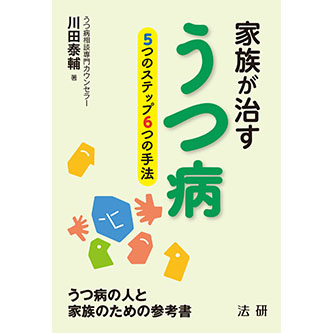
家族が治すうつ病
¥1,650患者を支える家族のための本―5つのステップ6つの手法うつ病の人と家族のための実用書
うつ病治療を医師に任せきりにして通院を重ねるだけでは、初期治療に失敗し、重症化・長期化させるケースがよくあります。
家族にも別の負担が重くのしかかります。
そのためうつ病の場合は特に医師に任せきりにせず、家族が積極的に関与していくことが大切です。
著者は、妻が重度のうつ病に苦しんだ経験の持ち主。
そのときの経験をもとに、うつ病患者の家族が直面する困難な状況に対処するメソッドを体系化しました。
本書では、うつ病で苦しんでいる患者と家族が、段階を追ってケースごとに対応できる方法をやさしく紹介します。 -
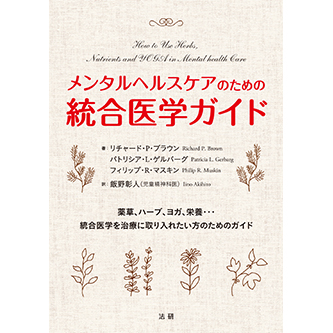
メンタルヘルスケアのための統合医学ガイド
¥3,850統合医学について科学的根拠を評価した本薬草、ハーブ、ヨガ、栄養・・・統合医学を治療に取り入れたい人のためのガイド統合医学について科学的根拠を評価した本
西洋医学と並んで、ヨガやハーブ、栄養、などによる治療や健康増進はこれまでも経験的に行われ、長い歴史を持ちます。西洋医学に比べるとなじみが薄く、信頼に足らない印象を持たれがちですが、こうしたものを組み合わせた統合医学を必要としている人も少なからずいるのです。
しかし、西洋医学を用いるのと同じように、知識を持たずに統合医学を導入することは危険です。情報が氾濫し、またその質が玉石混交である点も西洋医学と同様です。
本書は、メンタルヘルスを中心に、更年期、妊娠、性機能、発達障害、またがんなどの身体疾患について、統合医学、補完代替医療を用いることを検討する際の参考となるよう、各治療法が持つ研究データやその信頼性について詳しく解説した書籍で、2009年にアメリカで発刊されて話題となった「How to Use Herbs Nutrients & YOGA in Mental Health Care」を日本語翻訳したものです。
実際にアメリカで西洋医学の知識を持ち、診療を行っている医師である著者の経験や見解も多数紹介されています。
統合医学を学びたい方、またご自身やご家族のためによりよい治療法を探している方にお勧めです。 -
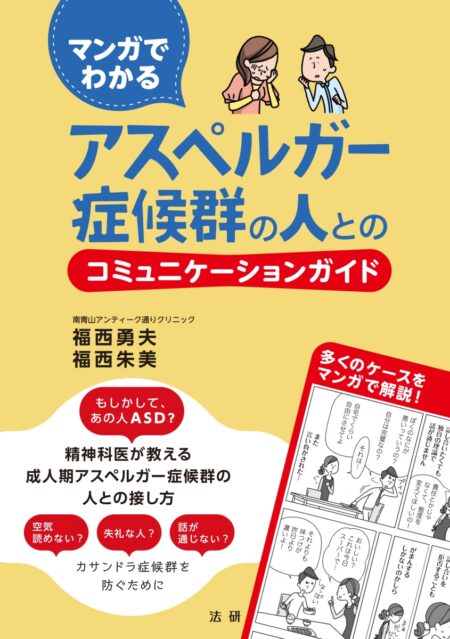
マンガでわかる アスペルガー症候群の人とのコミュニケーションガイド
¥1,760精神科医が教える成人期アスペルガー症候群の人との接し方カサンドラ症候群を防ぐために精神科医が教える
アスペルガー症候群の人とのコミュニケーションのヒント
誰でもコミュニケーションに悩むことはありますが、相手がアスペルガー症候群を始めとするASD(自閉症スペクトラム障害)など発達障害を抱えていることで、よりコミュニケーションが難しくなることがあります。コミュニケーションに悩み、心身に不調を来しているカサンドラ症候群と呼ばれる状態に陥ってしまう人も。また、障害を持つ当人も悩んでいます。
本書では、身近なアスペルガー症候群の人とのコミュニケーションに悩んでいる人向けに、コミュニケーションを難しくさせるアスペルガー症候群を中心とした発達障害の基礎知識、検査、診断、治療法、また問題を解消するために取り組んだ人の例をわかりやすく、豊富なマンガを用いて解説します。 -
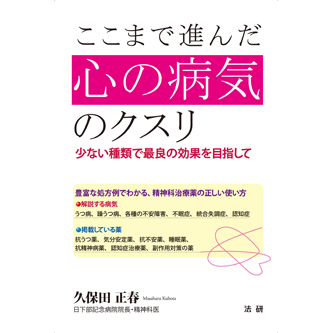
ここまで進んだ 心の病気のクスリ
¥1,650少ない種類で最良の効果を目指して貴重な処方例でわかる、精神科治療薬の正しい使い方豊富な処方例でわかる、精神科治療薬の正しい使い方
・心の病気の治療薬は多様です。「うつ病だから抗うつ薬」とも言い切れない面が多くあり、それは他の心の病気でも同様です。本書は症状・病状による各種の向精神薬の使い分けについて、実際の処方例を多く掲載しつつ具体的に解説。
「どんな薬が」「どんな時に」「どんな目的で処方されるのか」をよく知ることで、病気の治療をアシストします。
安全な多剤併用と避けたい多剤併用もわかり、なるべく少ない薬を有効に用いて最良の効果を得るための、患者さん向けガイドブックです。 -

家族ががんになりました
¥1,540がんと診断されたらまず読む本大切な人、そしてあなた自身のためにがんと戦うために心を守る
がんは2人に1人がかかる身近な病気です。その診断の衝撃は大きく、がんを受容しきる前にがんとの戦いが始まり、大きな心理的負担となります。近年、そうした状況で患者さんやご家族の心のケアが、がんそのものの治療にも欠かせないことが知られてきました。
ご家族ががんと診断されたときに
長年、がん治療に取り組む患者さんとご家族を見守り続けてきた、がんと心の関係の専門医である精神腫瘍医の著者が、がん治療の基礎知識など、ご家族に知っておいてほしいこと、患者さんの支え方、そしてご自身の心の守り方を豊富な事例とともにわかりやすく解説します。 -
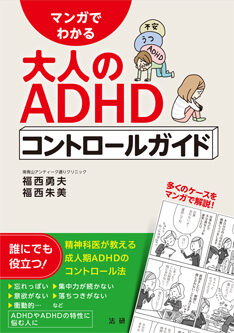
マンガでわかる 大人のADHDコントロールガイド
¥1,760誰にでも役立つ精神科医が教える成人期ADHDのコントロール法精神科医が教える
マンガ版成人期ADHDのコントロール法
忘れっぽい、集中力が続かない、意欲がない、落ちつきがない、衝動的…、ADHDやADHDの特徴に悩む人は大勢います。
本書はADHDの特性を持つ人のために、生活をコントロールして、トラブルを回避するための実践的なコツ、アドバイスを、豊富な臨床経験を持つ医師による解説と豊富なマンガで紹介します。日米の医療機関での研究や、実際のADHD患者が行って効果のあった取り組みから、考え方やヒントが得られます。
・マンガだから読みやすく、わかりやすい!
厚い本を読むのは苦手…という人でも気軽に読むことができます。
・ケーススタディから学べる!
ADHDは人それぞれ。豊富な事例から自分なりのコントロール法を見出せます。