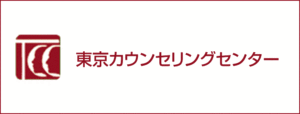信頼できる名医によるセカンドオピニオン取得をサポート
重い病気にかかったときほど、医師の技量によって医療ミスのリスクや、入院日数、医療費、生存率に差がでるため、信頼できる医師を選ぶことが重要となります。
ベストドクターズ・サービスは、テラドックヘルス社が独自の調査によって選出した信頼できる名医・専門医や医療機関をご案内するサービスです。保険会社様やカード会社様のハイクラスな付帯サービスとして利用され、高い評価をいただいております。
サービスの特徴
信頼できる医師をご案内
ベストドクターズ・サービスは、医師同士の相互評価にもとづいた信頼できる名医・専門医をご案内します。
ご案内する名医・専門医には事前にコンタクトを取り、案内・相談の承諾を得ています。そのため、案内されても実際には診てもらえないかもしれないなどという心配はありません。
「医師がベストとみなす医師」を選出
医師同士による相互評価(ピアレビュー調査)により、名医・専門医を選出いたします。
この調査は、医師に「自己または家族の治療を、自分以外の誰に委ねるか」という観点から、他の医師についての評価を伺うことで進められるものです。最終的に一定以上の評価を得た医師を名医・専門医(Best Doctors in Japan)として選出いたします。本調査の特徴は、医師のみによる医師に対する調査であり、完全な客観評価である点です。
さらに、定期的にこの調査を行うことで、名医・専門医のリストは更新され、調査ごとに最新の状態に保たれています。現在のBest Doctors in Japanは約7,100名(2024年6月現在)です。
サービスの内容
ご提供するサービスとして、テラドックヘルス社が独自の調査によって選出した信頼できる名医・専門医(ベストドクターズ選出医)をご案内する「ファインド・ベスト・ドック」、名医・専門医と電話で相談ができる「テレセカンド」、名医・専門医が所属する医療機関の情報をご案内する「ホスピサーチ」、というそれぞれ特長のある3つのサービスをご用意しており、お客様のニーズに合わせてサポートいたします。
ファインド・ベスト・ドック
ベストドクターズ選出医による治療
ベストドクターズ選出医によるセカンドオピニオン
サービス内容
優秀な専門医への受診をサポート
専門医同士の相互評価に基づいて選ばれた約7,100名(2024年6月現在)の優秀な専門医の中から、利用者に最適と思われる名医・専門医を選んでご紹介。受診までサポートします。
※専門医とは、独自調査によって選ばれた医師を指します。学会等認定の専門医ではありません。
ベストドクターズ選出医による治療までのサービスフロー
治療方針に不安があるなどに、医師をご案内します。
※入院・転院を目的としたサービスはありません。
ベストドクターズ日本コールセンタ―にご連絡いただいてから専門医を書類にてご案内するまでに約8日~10日かかります。
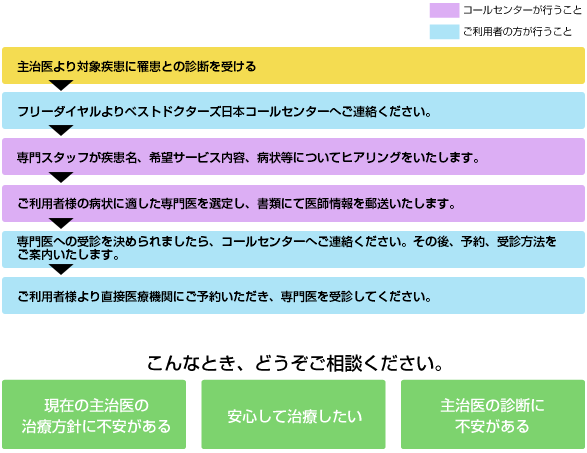
名医のセカンドオピニオンが受けられる
各分野の優秀な専門医によるセカンドオピニオン(主治医以外の第二の意見)が受けられます。
ベストドクターズ選出医によるセカンドオピニオン取得までのサービスフロー
他の医師の見解も聞き、納得できる治療法を選択したいときなど、セカンドオピニオンの取得を目的にご利用いただけます。ベストドクターズ日本コールセンタ―にご連絡いただいてから専門医を書類にてご案内するまでに約8日~10日かかります。
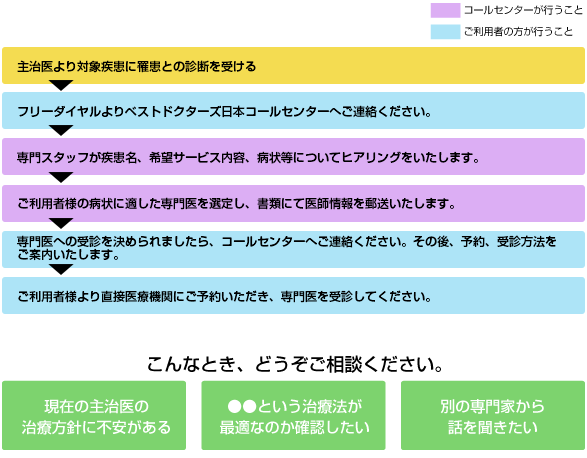
受診可能な名医をご案内します
ご案内する名医・専門医には事前にコンタクトを取り、受診の承諾を得ています。案内されても実際には診てもらえないなどという心配はありません。
経験豊かな看護師が親身に対応いたします
コールセンターのスタッフは全員が臨床経験豊かな看護師です。ご利用者様の気持ちを受け止め、医学的情報を確認しながらニーズの把握を行い、ご利用者様に最適と思われる名医・専門医を選択し、医師とご利用者様とのパイプ役となります。
【対象疾患】
現在の対象となる疾病は以下の通りです。予告なく変更される場合もございますので、詳しくは弊社までお問い合わせください。
- すべてのがん(例:大腸がん、子宮がん、悪性リンパ腫 など)
- 心臓疾患(原則、手術適応)(例:狭心症、大動脈弁狭窄症 など)
- 脳(神経)疾患(原則、手術適応)(例:良性脳腫瘍、未破裂脳動脈瘤 など)
- 膠原病
- 難病の一部(例:パーキンソン病、筋ジストロフィー など)
- 眼科疾患の一部(原則、手術適応)(例:白内障、緑内障 など)
- 整形外科疾患の一部(原則、手術適応)(例:脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニアなど)
- 婦人科疾患の一部(原則、手術適応)(例:子宮筋腫、子宮内膜症 など)
- 肝臓病の一部(原則、手術適応)
※ご利用いただく場合は、対象疾患と診断されていることが必要です。(「疑い」の状態ではご利用いただけません)。
※地域やご相談内容によりご要望に沿えない場合があります。
※緊急手術が必要な場合、また救急対応ではご利用いただけません。
※治療費等医療機関での受診費用は、すべてご利用者負担となります。
※入院・転院を目的としたサービスではありません。
※日本国内の医師のみの照会となります。
※対応言語は日本語のみです。
テレセカンド
ベストドクターズ選出医と電話でご相談
サービス内容
満足感の高い相談が可能
相談時間は病院のセカンドオピニオンと同水準です。
状況を伺い、医師に連携
病状や希望をお聞かせください。臨床経験を積んだ看護師がご相談に応じる医師を検索、相談日時を設定します。
名医相談に立会いサポート
看護師が三者通話で電話相談に立会いしっかりサポート。難しい医療用語は丁寧に解説します。
名医との相談後もご支援
名医と電話相談後に何かご心配がある場合は、担当看護師がフォローします。
医師との電話相談は予約制です。相談日時はご利用者様とお打ち合わせの上、決定いたします。相談日の目安は、利用申込日から2週間以内です。
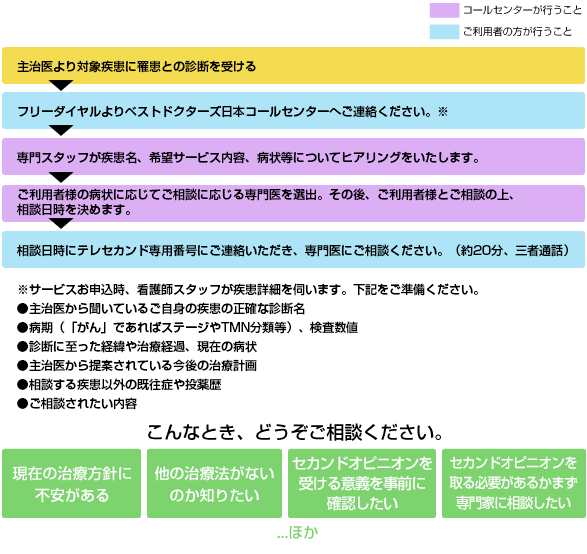
ホスピサーチ
ベストドクターズ選出医のいる病院をご紹介
サービス内容
お客様の相談にスピード対応
お電話ですぐに情報をお伝えすることが可能です。
名医がいるという安心
ご案内は必ずベストドクターズ選出医が在籍する病院・診療科になります。
お電話をいただいたら、その場で情報をお伝えします。
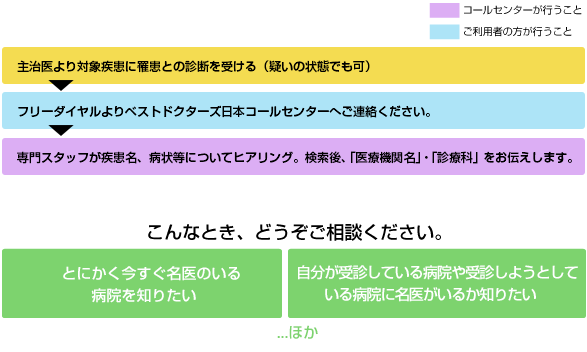
【対象疾患】
現在の対象となる疾病は以下の通りです。予告なく変更される場合もございますので、詳しくは弊社までお問い合わせください。
- すべてのがん(例:大腸がん、子宮がん、悪性リンパ腫 など)
- 心臓疾患(原則、手術適応)(例:狭心症、大動脈弁狭窄症 など)
- 脳(神経)疾患(原則、手術適応)(例:良性脳腫瘍、未破裂脳動脈瘤 など)
- 膠原病
- 難病の一部(例:パーキンソン病、筋ジストロフィー など)
- 眼科疾患の一部(原則、手術適応)(例:白内障、緑内障 など)
- 整形外科疾患の一部(原則、手術適応)(例:脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニアなど)
- 婦人科疾患の一部(原則、手術適応)(例:子宮筋腫、子宮内膜症 など)
- 肝臓病の一部(原則、手術適応)
※地域やご相談内容により、ご要望に沿えない場合があります。
※本サービスでは医師名は一切ご案内いたしません。