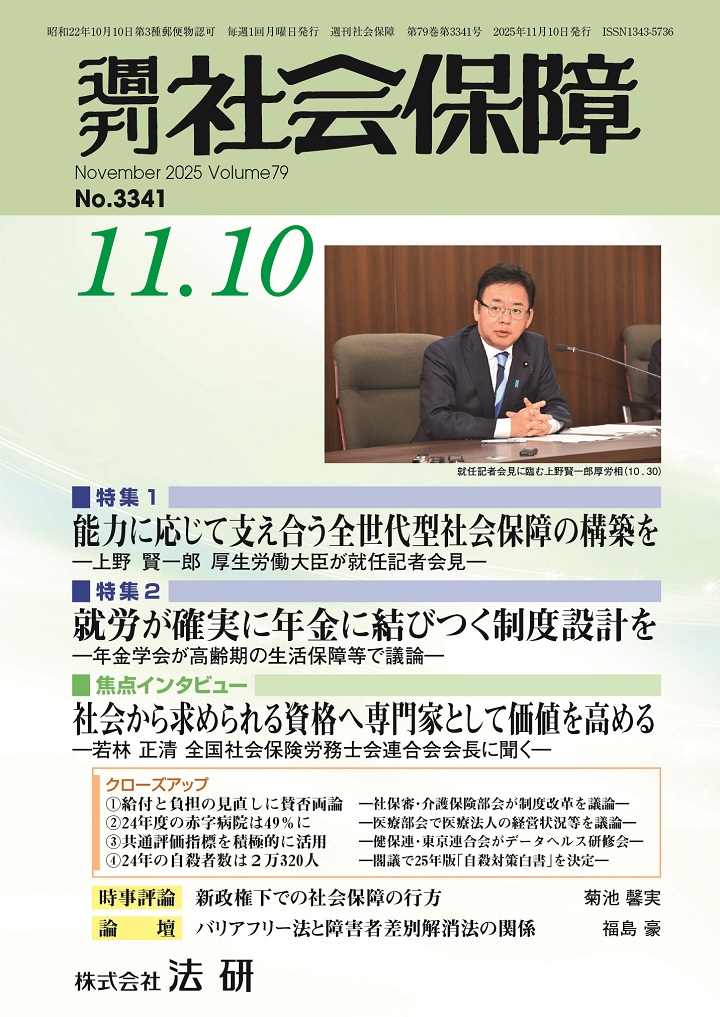社会保障全般
▼政府は10月24日、「令和6(2024)年度我が国における自殺の概況及び自殺対策の実施状況」(2025年版自殺対策白書)を閣議決定。特集は「若者の自殺をめぐる状況と電話・SNS等を活用した相談事業」(P.15)
厚生労働行政
▼政府は10月25日の閣議で、2025年秋の叙勲の勲章受章者を決定し、11月3日に発令。厚生労働関係では、金子順一氏(元厚生労働事務次官、瑞宝重光章)をはじめ403人が受章(P.17)
▼政府は10月25日の閣議で、2025年秋の緑綬・黄綬・藍綬褒章受章者を決定し、11月3日に発令。厚生労働省関係は、緑綬褒章が19人、黄綬褒章は85人、藍綬褒章は黒瀨巌氏(現日本医師会常任理事)ら59人の計163人(P.18)
▼上野厚労相は10月30日、専門誌記者クラブの就任記者会見に臨み、「社会保障給付費は今後も増加することが見込まれる。能力に応じて全世代が支え合う、全世代型社会保障の構築に向けて、社会保険料の負担軽減を図りながら制度の持続可能性を高めることが重要な課題」との考えを示す(P.6)
医療・医療保険
▼社保審・医療部会は10月27日、①医療機関の業務効率化・職場環境改善の推進、②医療法人の経営状況、③2026年度診療報酬改定の基本方針について議論。24年度に医業収支が赤字の病院は59.7%(P.12)
▼中医協は10月29日、費用対効果評価専門部会と薬価専門部会と保険医療材料専門部会の合同部会、薬価専門部会、総会を開催。総会では、療養病棟入院料2の「医療区分2・3の患者割合が5割以上」という要件の厳格化について議論(P.16)
▼健保連・東京連合会は10月31日、2025年度データヘルス研修会を開催。26年度に控えるデータヘルス計画の中間評価・見直しに向け、厚労省、支払基金、健保連本部の担当者が講演。厚労省は健保組合共通評価指標の活用と保健事業のパターン化の重要性、支払基金は健康スコアリングレポートの集計データの分析方法、健保連は2025年度医療DX補助金の申請状況等を説明(P.14)
年 金
▼日本年金学会は10月23、24日、総会・研究発表会を開催。24日には、共通論題「社会保障の持続可能性を踏まえた高齢期の生活保障の在り方について」を共通論題に、研究発表、基調講演、シンポジウムを行った。東北大学公共政策大学院の度山徹教授が、今後の社会経済の変化に対応した制度改正の展望等をテーマに基調講演(P.22)
介 護
▼社保審・介護保険部会は10月27日、持続可能性の確保、介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営改善支援等、地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方)について議論。給付と負担の見直し(持続可能性の確保)に関する検討については、賛否両論の意見があった(P.10)
時事評論
新政権下での社会保障の行方
早稲田大学理事・教授 菊池 馨実
論 壇
バリアフリー法と障害者差別解消法の関係
関西大学教授 福島 豪