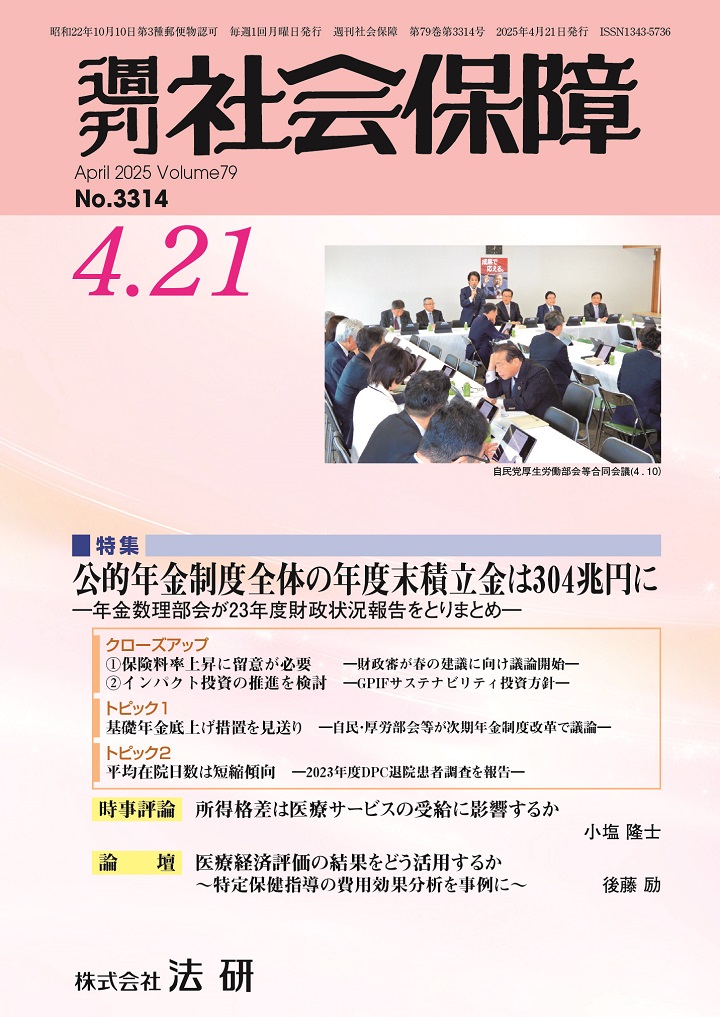国 会
▼参院厚労委は4月10日、安衛法等改正案の質疑後、討論を経て採決し、自民、立憲、公明、維新、民主の賛成多数で可決。翌11日の参院本会議で可決、衆院へ送付。また、16項目の附帯決議を採択(P.15)
社会保障全般
▼財政審は4月9日、春の建議に向けた議論を開始。財務省事務局が提出した「財政総論」では、人口減少下での経済財政政策の必要性を指摘。社会保障については、医療・介護の給付と負担の改革や所得再分配機能の再検討等の方向性を示す(P.12)
▼諮問会議は4月10日、有識者議員が提出した「経済再生と財政健全化の両立に向けて」を踏まえ、議論。有識者議員は、「社会保障の持続性確保と機能の向上には、現役世代の負担を軽減し、誰もが年齢にかかわらず能力や個性を生かして支え合う全世代型社会保障の構築が不可欠」と指摘(P.15)
医療・医療保険
▼厚労省は3月31日、2023年度DPC導入の影響評価に係る調査(退院患者調査)結果を公表。平均在院日数は、大学病院本院群が11.50日、DPC特定病院群が11.07日、DPC標準病院群が11.69日で、いずれも前年度から短縮(P.36)
▼社保審・医療保険部会柔整療養費検討専門委は3月31日、厚労省事務局が「柔道整復療養費のオンライン請求導入等について(中間とりまとめ)」を報告し、意見交換。基本的な考え方や個別の検討項目の方向性等を整理しており、「すべての保険者等が参加する仕組みを目指す必要がある」等と指摘(P.16)
▼中医協は4月9日、診療報酬改定結果検証部会、総会を開く。総会では、次期(2026年度)診療報酬・薬価改定に向けた議論の進め方について、9月末頃までに1巡目の議論を終え、10月頃から2巡目の議論に入り、来年2月頃の答申を目指す(P.14)
年 金
▼社保審・年金数理部会は3月27日、2023年度の公的年金財政状況報告をとりまとめ。公的年金制度全体の単年度収支状況は、運用損益分を除いた収入総額が54.4兆円、支出総額54.5兆円、単年度収支残は△0.1兆円。時価ベースの運用損益は+53.6兆円で年度末積立金は304兆円。被保険者数は国民年金第1号及び第3号被保険者が減少したものの、厚生年金の被保険者が増加したことから、公的年金制度全体ではほぼ横ばい(P.6)
▼GPIFは3月31日、「サステナビリティ投資方針」を策定。「サステナビリティに関するリスクの低減や市場の持続可能性の向上」と「市場平均収益率の確保」の両立を図ることで、ポートフォリオ全体の長期的なパフォーマンス向上への貢献を目指す(P.13)
▼自民・厚労部会等は4月10日、次期年金制度改革について関係団体等のヒアリングにおける指摘への対応について議論。厚労省は、被用者保険の適用拡大等の改革案の効果等を説明した資料を示す。17日には、厚労省が基礎年金底上げ措置の見送りを表明(P.22)
時事評論
▼所得格差は医療サービスの受給に影響するか
一橋大学特任教授 小塩 隆士
論 壇
▼医療経済評価の結果をどう活用するか
~特定保健指導の費用効果分析を事例に~ 慶應義塾大学大学院教授 後藤 励